加齢黄斑変性症は、主に高齢者にみられる目の病気です。視力の中心を担う黄斑に変化が起こり、見えにくさやゆがみなどの症状が生じます。欧米では中途失明の大きな原因のひとつとされてきましたが、日本でも近年患者数が増加しています。
かつては治療が難しいとされていましたが、近年は進行を抑える治療法が確立されつつあり、早期発見と継続的なケアが重要とされています。この記事では、誰にとっても身近な眼疾患である加齢黄斑変性症の原因や症状、診断・治療の方法、日常でできる予防策までをわかりやすく解説します。
加齢黄斑変性症の基礎知識
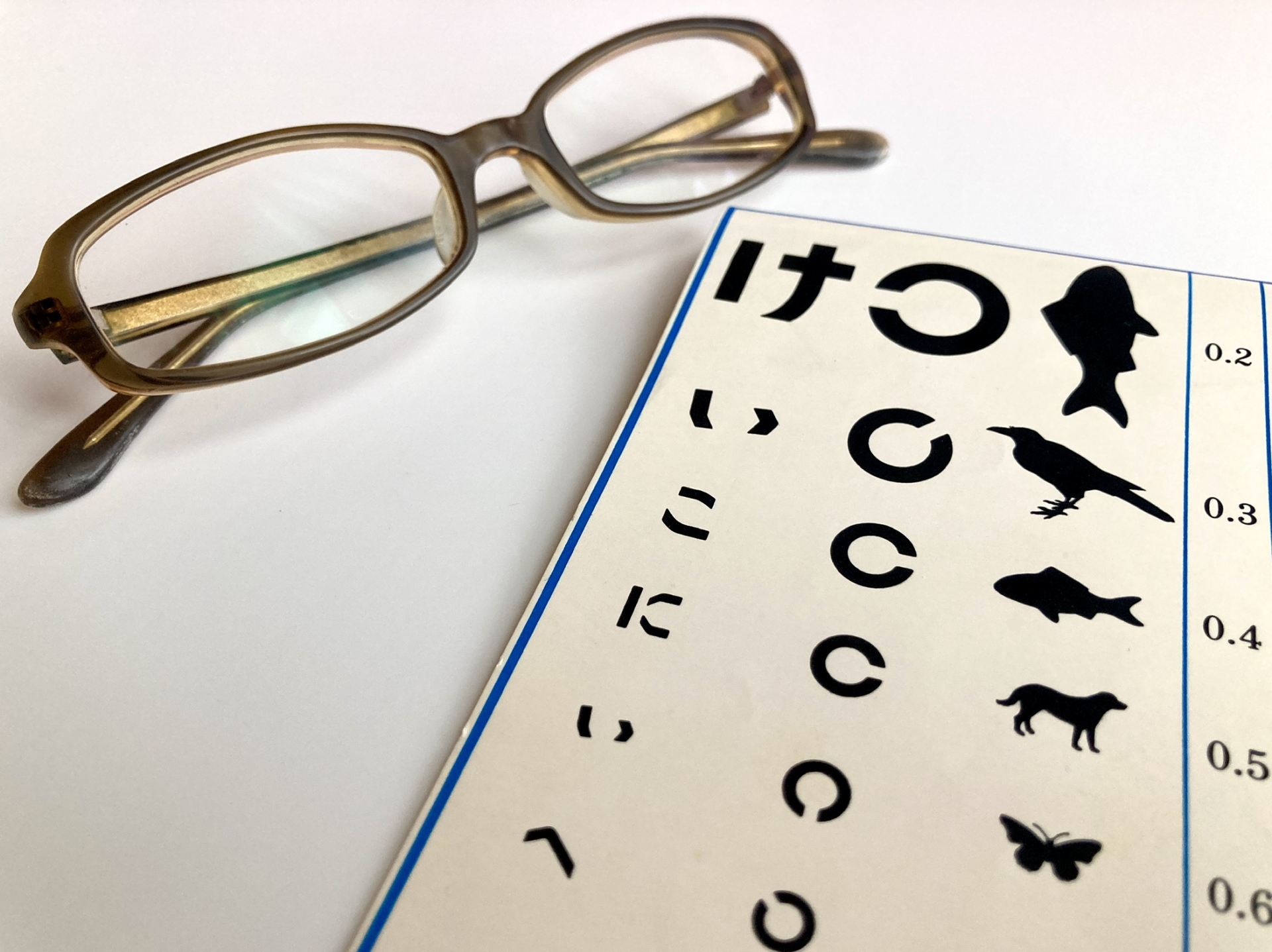 加齢黄斑変性症とは、加齢に伴って目の奥にある網膜の中心部分(黄斑(おうはん))が障害され、視力が低下していく病気です。網膜はカメラでいうところのフィルムにあたる部分で、特に黄斑は細かいものを見るために重要な働きを担っています。
加齢黄斑変性症とは、加齢に伴って目の奥にある網膜の中心部分(黄斑(おうはん))が障害され、視力が低下していく病気です。網膜はカメラでいうところのフィルムにあたる部分で、特に黄斑は細かいものを見るために重要な働きを担っています。
この病気が進行すると、網膜の中心にむくみや出血が生じ、物がゆがんで見えたり、視界の中心が見えにくくなったりします。放置すると回復が難しくなり、生活に支障をきたすこともあります。
ここではまず、加齢黄斑変性症の基礎知識について解説します。
加齢黄斑変性症の原因
加齢黄斑変性症は、その名のとおり加齢が要因となって発症する目の病気です。
年齢を重ねることで、目の奥にある黄斑という組織の働きが衰え、老廃物がうまく処理されなくなります。これにより、黄斑に不要な物質がたまり、周囲の細胞に悪影響を与えると考えられています。
また、紫外線によるダメージ、喫煙の習慣、遺伝的な要因、さらには食生活や運動不足などの生活習慣も影響すると考えられています。
加齢黄斑変性症の典型的な症状
加齢黄斑変性症の初期には、自覚しにくい場合もありますが、病気が進行すると次のような症状が現れることがあります。視野が欠けたり、見え方に変化が現れたりします。
◎ものがゆがんで見える変視症
直線が波打って見えたり、物の形がゆがんで見えたりします。これは、網膜の中心がむくんだり変形したりすることで起こる現象です。例えば、ドアの枠やタイルの目地が曲がって見えるなど、日常生活のなかで気付くことがあります。
◎視力の低下や、視界の中心が暗くなる中心暗点
物の中心部分が見えにくくなり、文字が読みづらくなったり、人の顔がぼやけて見えたりします。視力が下がることで、本を読むことや車の運転などが困難になるケースもあります。
◎色の見え方が変化する色覚異常
加齢黄斑変性症が進行すると、色の違いがわかりにくくなったり、色味が鈍く感じられたりするようになります。赤や緑、青といった基本的な色も、以前とは違って見えることがあります。
加齢黄斑変性症を発症しやすい年齢層
加齢黄斑変性症は、主に50歳以上の中高年から高齢者にみられる病気です。年齢が上がるにつれて発症率も高くなる傾向があり、特に70代以降では有病率が顕著に増加します。
福岡県の久山町で行われた調査によると、50歳以上の0.87%がこの病気を発症しているという結果が出ています。高齢化が進む日本では、今後さらに患者数が増えることが懸念されており、早期発見と予防の重要性が高まっています。
男女差でみると、男性が発症しやすい傾向にあるとされていますが、生活習慣や環境、遺伝的背景によって個人差が大きいため、誰にでも起こりうる病気といえます。
加齢黄斑変性症のタイプ
 加齢黄斑変性症は、滲出型(しんしゅつがた/ウェット型)と萎縮型(いしゅくがた/ドライ型)の2つに分けられます。日本では、視力への影響が強い滲出型の患者さんが多く、全体の約9割を占めるといわれています。一方、萎縮型は欧米人に多く見られます。
加齢黄斑変性症は、滲出型(しんしゅつがた/ウェット型)と萎縮型(いしゅくがた/ドライ型)の2つに分けられます。日本では、視力への影響が強い滲出型の患者さんが多く、全体の約9割を占めるといわれています。一方、萎縮型は欧米人に多く見られます。
滲出型(ウェット型)
滲出型は、網膜の下やなかに異常な新しい血管(新生血管)ができることで発症します。この新生血管はとてももろく、血液やその成分が周囲に漏れ出すため、出血やむくみ(浮腫)を引き起こします。
この漏れ出た物質が黄斑部にダメージを与えることで、視力の低下や変視症などの症状が現れます。進行が速い傾向があり、早期の発見と治療が重要です。
萎縮型(ドライ型)
萎縮型は、新生血管は関係せず、網膜の細胞や組織が徐々に萎縮していくことで黄斑の機能が低下していくタイプです。進行はゆっくりで、初期には自覚症状が出にくいこともあります。
現時点では有効な治療法が確立されておらず、症状が進まないよう経過を観察するのが基本的な対応です。ただし、萎縮型が後に滲出型へ移行するケースもあるため、定期的な眼科での検査が勧められます。
加齢黄斑変性症の診断方法
 加齢黄斑変性症の診断方法について解説します。一般的に、眼科ではいくつかの検査を組み合わせて、網膜や黄斑の状態、新生血管の有無や進行状況を確認します。
加齢黄斑変性症の診断方法について解説します。一般的に、眼科ではいくつかの検査を組み合わせて、網膜や黄斑の状態、新生血管の有無や進行状況を確認します。
眼底検査・OCT(光干渉断層計)による網膜の評価
加齢黄斑変性症の診断では眼底検査が行われます。眼底とは目の奥にある網膜や視神経の部分を指し、専用の機器で直接観察したり、写真を撮ったりして黄斑の状態を確認します。
検査方法には、通常のカラー写真を撮るものと、造影剤(ぞうえいざい)という薬剤を腕の血管から注射し、血管の異常を詳しく調べる方法があります。造影検査では、新生血管の有無や、血液が漏れ出していないかを確認できます。
近年では、OCTを用いて検査をするのが一般的です。OCTという検査では、網膜を断面図として映し出し、むくみの程度や網膜の層構造、新生血管の存在などを立体的に評価できます。数秒で終わる検査で、造影剤を使わないため身体への負担も少なく、経過観察にもよく用いられます。
蛍光眼底造影による血管の検査
蛍光眼底造影は、加齢黄斑変性症に特徴的な新生血管の状態を詳しく調べるための検査です。検査では、蛍光色素を含んだ造影剤を腕の静脈から注射し、目の奥にある網膜や脈絡膜の血管の様子をカメラで連続的に撮影します。血液の流れや漏れの有無、血管の形状や広がりを可視化することで、異常の有無を判断します。
使用される造影剤には主に2種類あります。一つはフルオレセインと呼ばれるもので、主に網膜の血管を観察するために使われます。もう一つはインドシアニングリーンと呼ばれる造影剤で、より深い部分にある脈絡膜の血管を詳しく調べる際に使用されます。
この検査によって、新生血管がどこにできているのか、どのような性質を持っているのか、そしてそこからどれだけ水分が漏れ出しているのかを把握することができます。
アムスラーチャートによる見え方のチェック
アムスラーチャートは、碁盤の目のような方眼図を見ながら、ゆがみや欠けを調べる簡単な検査です。患者さんは黒い点を中心に見つめながら、周囲の線が曲がって見えないか、途切れていないかを確認します。医療機関だけでなく自宅でも実施可能です。
加齢黄斑変性症の治療方法
 加齢黄斑変性症の治療は、病気のタイプや進行の程度に応じてさまざまな方法があり、複数の治療法を組み合わせることもあります。ここでは代表的な4つの治療法をご紹介します。
加齢黄斑変性症の治療は、病気のタイプや進行の程度に応じてさまざまな方法があり、複数の治療法を組み合わせることもあります。ここでは代表的な4つの治療法をご紹介します。
硝子体内注射
滲出型加齢黄斑変性の主な原因は、脈絡膜新生血管と呼ばれる異常な血管の発生です。これらの血管は、VEGF(血管内皮増殖因子)というたんぱく質によって成長が促進されます。
硝子体内注射では、このVEGFの働きを抑える薬剤を使って、新生血管の発育や漏れを抑制します。硝子体内注射は目に直接薬剤を注射します。局所麻酔をしたうえで行うため、痛みはほとんどなく、外来で受けられる治療です。
治療スケジュールは個々の病状によって異なりますが、一般的には初めに毎月1回、3回連続で注射を行い、その後は必要に応じて投与間隔を調整しながら継続します。
効果には個人差があり、長期的に注射を続ける必要がある場合も多く、中断すると再発することがあるため、根気強く治療を続けることが大切です。
光線力学的療法
光線力学的療法は、光に反応する薬剤(ベルテポルフィン)を体内に注射した後に、弱いレーザーを病変部に照射して、新生血管を閉じる治療です。かつては単独で行われていましたが、現在では抗VEGF薬との併用治療として使われることが多くなっています。
治療は通常、3ヶ月ごとに経過を見ながら繰り返し行います。治療後しばらくは、体内に薬剤が残っており、日光や強い照明に当たると肌に炎症が起きることがあります。そのため、治療後5日間程度は外出を控え、帽子や長袖、手袋などで紫外線を避ける対策が必要です。
レーザー光凝固術
新生血管が視力の中心にあたる部分(中心窩)を避けて存在している場合は、レーザーを使って新生血管を焼き切る治療が行われることがあります。この方法では、レーザーを当てた部分の網膜が損傷を受け、その部分の視野は失われますが、新生血管の拡大を防ぐことで、病状の進行を抑える効果が期待されます。
硝子体手術
網膜の下に大量の出血が起こった場合や、硝子体に出血が広がった場合には、硝子体手術が選択されることがあります。この手術では、まず濁った硝子体を取り除き、同時に出血を除去します。その後、必要に応じて光凝固(レーザー照射)や異常な膜の除去、止血処置などを行います。
手術の際には眼内に空気やガス、シリコンオイルといった物質を注入することがあります。これらは網膜の安定を保つために用いられます。
手術後は、注入した物質の種類や状態によってうつ伏せ姿勢を一定期間保つ必要があります。特にガスを使った場合は、2~3週間は仰向けで寝ないように注意が必要です。ガスや空気は自然に吸収され、やがて眼内液に置き換わりますが、シリコンオイルを使用した場合は、後日除去手術を行うことがあります。
日常生活でできる加齢黄斑変性症の予防策
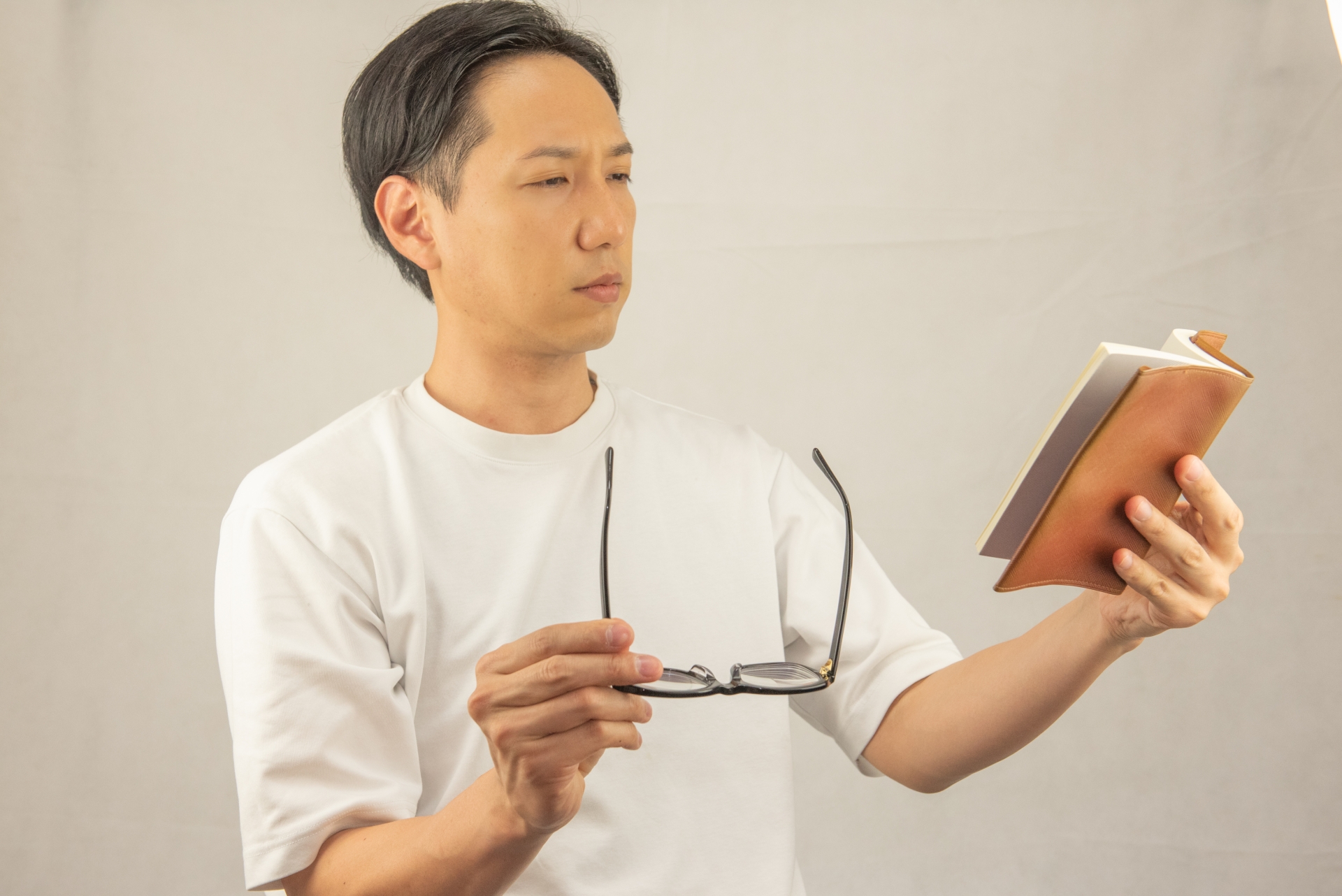 加齢黄斑変性症は加齢によって発症リスクが高まる病気ですが、日常の生活習慣を見直すことで予防につなげることができます。ここでは、普段の生活で意識したいポイントを紹介します。
加齢黄斑変性症は加齢によって発症リスクが高まる病気ですが、日常の生活習慣を見直すことで予防につなげることができます。ここでは、普段の生活で意識したいポイントを紹介します。
目によい栄養素を積極的に摂取する
網膜の細胞を守るためには、抗酸化作用のある栄養素を含む食品を積極的に摂ることが大切です。ビタミンE・ビタミンC・ベータカロテンなどを含むミカン、ニンジン、カボチャ、大豆、玄米といった食品や、亜鉛を多く含む牡蠣や海藻類が効果的です。 黄斑を保護する働きのあるルテインを含むホウレンソウやケール、ブロッコリーなどの緑黄色野菜もおすすめです。さらに、オメガ3脂肪酸を含むイワシやアジ、サンマなどの魚をとることで、炎症を抑える働きも期待できます。
これらの栄養素を補うには、サプリメントの服用も選択肢のひとつです。サプリメントについては、海外の大規模研究で有効性が示された成分を含む製品もあります。すでに発症している方や、眼底検査で前兆がみられる方は、医師と相談したうえで補助的に取り入れるとよいでしょう。
紫外線とブルーライトから目を保護する
紫外線は網膜にダメージを与え、加齢黄斑変性の発症リスクを高めるとされています。屋外ではUVカット機能のあるサングラスや帽子を使って目を守ることが大切です。
パソコンやスマートフォンなどのブルーライトも目への負担となるため、長時間の使用を避け、必要に応じてブルーライトカット眼鏡などを活用するとよいでしょう。
禁煙や運動で高血圧を防止する
喫煙は加齢黄斑変性を引き起こす危険因子のひとつです。喫煙で血管が傷つき、網膜への血流や酸素の供給が悪くなることが知られています。禁煙は予防のうえでもっとも優先すべき対策といえるでしょう。どうしてもやめられない方は、禁煙外来の受診も検討してみてください。
また、高血圧や脂質異常症といった生活習慣病も発症リスクを高めるため、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけることが重要です。
まとめ
加齢黄斑変性症は、加齢に伴って誰にでも起こりうる目の病気です。初期には気付きにくいこともありますが、進行すると視力への影響が大きく、日常生活に支障をきたすこともあります。
早期発見・早期治療が視力を守るカギとなるため、定期的な眼科検診やセルフチェックが重要です。加えて、日々の生活習慣を見直すことも予防につながります。気になる症状がある場合は、早めに眼科を受診しましょう。
参考文献
