近視は一般的な視力の問題ですが、そのなかでも特に度数が強い強度近視は単にメガネが厚くなるだけでなく、さまざまな目の病気のリスクを高める可能性があります。本記事では、強度近視とは何か、その定義や見え方、通常の近視との違い、さらに強度近視が引き起こしうる合併症について解説します。また、強度近視で失明する確率や、強度近視および合併症に対する治療法、そして強度近視を防ぐためにできる対策についても解説します。本記事を読むことで、強度近視に対する理解が深まります。
強度近視とは

強度近視はほかの近視とどう違うのでしょうか。近視の分類から定義、その見え方などを詳しく解説します。
近視の分類
近視はその強さによって以下のように分類されます。
- 弱度近視(軽度近視): -0.5D以上 -3.0D未満の近視のこと
- 中等度近視:-3.0D以上 -6.0D未満の近視のこと
- 強度近視(高度近視):-6.0D以上の強い近視のこと
このように近視の程度を数値で分類しますが、強度近視だから病気というわけではありません。前述のように、強度近視の方でも適切に矯正すれば多くの場合は良好な視力を維持できます。重要なのは、強度近視のなかで眼底に変性や障害を生じた状態(病的近視)かどうかです。次の章では強度近視の正式な定義や見え方、視力との関係について詳しく説明します。
強度近視の定義

強度近視は一般的に近視度数が-6.0Dを超える場合に分類されます。これは例えば、裸眼で焦点が合う距離が20cmより短いような状態に相当します。実際、ディオプター(D)は1 ÷ 焦点距離(m)で計算されるため、裸眼で50cm先にピントが合う方は約-2.0D、20cm先なら約-5.0Dの近視度数ということになります。-6.0Dの方の遠点は約16~17cmと近く、これより遠い物体は裸眼ではピントが合わずぼやけてしまいます。また、眼軸長(角膜から網膜までの長さ)の指標でも約26.5mm以上が強度近視とされます。眼軸長と近視度数には相関があり、眼軸長が1mm伸びるとおよそ-3D程度近視が進むとも言われます。
強度近視では眼球の奥行きが長いために網膜が引き伸ばされ、結果として網膜が薄くなったり弱くなったりします。このため近視の度数が強い方ほど、将来的に眼の病気を発症するリスクが高まることがわかっています。具体的には、後述するような網膜や黄斑部の病変のほか、緑内障や白内障などさまざまな疾患が生じやすくなります。
強度近視の見え方
強度近視の方が感じる見え方の特徴として、裸眼では遠くはもちろん、中間距離や場合によっては手元ですらピントが合いにくいことが挙げられます。中等度近視までであれば、裸眼でも近く(30cm前後の読書距離)はある程度見える場合があります。しかし、-6Dを超える強度近視になると、裸眼で鮮明に見えるのは顔のすぐ前のわずかな距離(十数cm程度)だけになります。例えば、-8Dの強度近視では目の前約11cmまで近づかないとはっきり見えない状態です。それより離れた日常的な距離では、物の輪郭や文字がぼやけて判別できなくなります。
このため強度近視の方は眼鏡やコンタクトレンズがないと生活が困難です。朝起きて枕元の眼鏡を探すのにも苦労したり、お風呂でシャンプーのボトルが識別できなかったりといった経験を持つ方も多いでしょう。裸眼視力にすると0.1を下回り、視力表の一番大きなランドルト環(Cの字)の向きも判別が難しいレベルです。
一方で、適切な度数のメガネ・コンタクトを装用すれば多くの場合は1.0前後の視力が出ます。強度近視だからといって矯正後の視力まで低下するわけではなく、眼自体に病変がなければ矯正視力は正常に保てます。ただし、後述する網膜の変性や視神経の障害が起きてしまうと、矯正視力が下がってしまうことがあります。
近視の度数と視力の違い
しばしば混同されやすいですが、近視の度数と視力は異なる概念です。度数は目のピントのずれ具合を表す光学的な指標で、-○Dという値で表現されます。一方、視力は視覚の鋭敏さ(どれだけ細かい物を識別できるか)を表す値で、一般的な視力表では1.0や0.1といった小数で示される指標です。
近視の度数が大きいほど裸眼視力が低下する傾向はありますが、両者に厳密な換算関係はありません。例えば「-6.0Dだから裸眼視力が0.01」といった単純な対応づけはできないのです。しかし大まかには、-6D以上の強度近視では裸眼視力0.1以下になるケースが多く、-10Dを超えるような場合には裸眼では0.01しか出ないこともあります。重要なのは、これらは矯正しない場合の視力であるという点です。適切な度数のレンズで矯正すれば、網膜にきちんと像を結ばせることができるため、多くの強度近視の方は1.0近い視力を取り戻せます。
強度近視の合併症
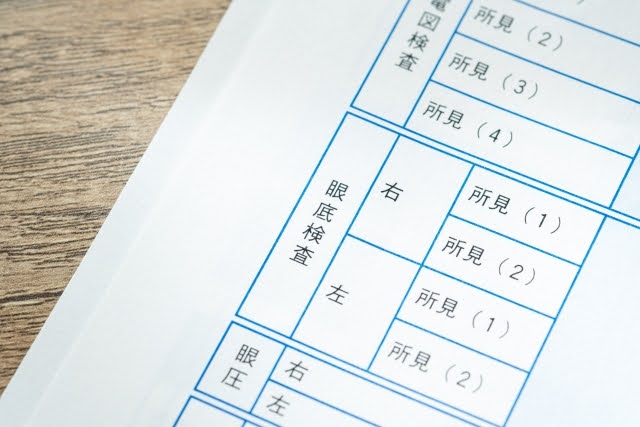
強度近視の怖いところは、近視が強いほど目の中でさまざま合併症を引き起こしやすくなる点です。眼球が大きく伸展することで、特に黄斑や視神経の周囲に負担がかかり、近視が強い方に特有の網膜および脈絡膜の障害が生じてきます。以下の3つが代表的です。
- 黄斑部出血(近視性脈絡膜新生血管)
- 近視性牽引黄斑症
- 近視性視神経症
これらはいずれも強度近視の方に起こりうる合併症であり、放置すると重篤な視力障害を引き起こす恐れがあります。それぞれの詳しい内容を順に見ていきましょう。
黄斑部出血
黄斑部出血とは、網膜の中心部である黄斑に出血が起こる状態です。強度近視の患者さんの約1割に、この黄斑部への出血が生じるとされています。眼球が伸びることで網膜を支えるブルッフ膜にひび割れが入り、その裂け目から網膜の下にある脈絡膜から新生血管が侵入・増殖してしまいます。本来は存在しない異常な血管(脈絡膜新生血管)が網膜下に生えると、もろい血管なので出血を起こしやすく、ちょうどそれが黄斑の下で出血すると中心視力に大きな影響が出ます。
近視性牽引黄斑症
近視性牽引黄斑症とは、強度近視眼で眼球が伸びきるのに網膜が追いつかず、黄斑部の網膜に裂け目や剥離が生じる病態です。強度近視の約1割にみられる合併症で、早期には自覚症状がほとんどないといわれているため発見されにくいですが、進行すると黄斑円孔や網膜剥離に発展し、重篤な視力障害を招く恐れがあります。
近視性視神経症
近視性視神経症とは、強度近視に関連して起こる視神経の障害の総称です。強度近視の眼では眼球の後部が長く伸びるため、視神経乳頭が変形や傾斜しやすくなり、さらに視神経線維自体も引き伸ばされて傷つきやすくなります。その結果、視野が徐々に欠けていくという症状が現れます。強度近視の方は眼圧が正常範囲でも視神経が障害されやすいため、正常眼圧緑内障を発症しやすいともされています。
強度近視で失明する確率

強度近視は、その合併症の有無によって失明のリスクが大きく変わります。網膜や視神経の障害を伴った病的近視に進行した場合、放置すると失明に至る確率が高まります。
実際、日本における視覚障害の原因疾患の順位では、強度近視は第5位と報告されています。これは緑内障、糖尿病網膜症、網膜色素変性、加齢黄斑変性に次ぐ位置で、日本人の失明原因の約数%を占めていると推計されます。
特に、先進国では強度近視(病的近視)が失明原因の上位に挙げられており、日本を含む東アジアで強度近視による視覚障害が大きな問題になりつつあります。
しかし、強度近視だからといって必ず失明に至るわけではありません。強度近視の方のほとんどは生涯にわたり良好な矯正視力を保つことができ、きちんと矯正し定期的に検診を受けて管理していれば過度に恐れる必要はありません。実際、強度近視でも病的な変化を起こさず高齢になっても眼鏡で1.0の視力を維持している方もいます。重要なのは、合併症を早期に発見し適切に対処することです。
一方で、病的近視へ移行し黄斑部に新生血管が発生した場合などは、適切な治療をしないと視力が大幅に低下し失明状態になるリスクが高くなります。かつて治療法が確立していなかった時代の研究では、病的近視の新生血管を放置した場合、5年で89%、10年で96%の眼が矯正視力0.1未満にまで視力が低下したと報告されています。これはほぼ生活が困難なレベルの重度視力障害です。
強度近視と合併症の治療法

強度近視になった場合の治療法とその合併症になった場合の治療法は異なります。本章では、そんな強度近視になった場合の治療法と合併症の治療法について解説します。
強度近視の治療法
強度近視そのものを根本的に治す方法は現時点では存在しません。しかし、視力を出すための矯正方法はいくつかあります。基本的にはメガネやコンタクトレンズによる矯正が第一です。
強度近視用の眼鏡レンズは度数が強いためかなり厚く重くなりがちですが、最近では高屈折率素材のレンズで薄型で軽量化が可能です。
コンタクトレンズは角膜に直接乗せるため強度近視でも視界の歪みが少なく、眼鏡よりも自然な見え方が得られる利点があります。特に-10Dを超えるような超強度近視の場合、眼鏡よりコンタクトの方が実用的なことも多いでしょう。
近視を屈折矯正手段以外で改善する方法として屈折矯正手術があります。代表的なレーシック手術は角膜を削って度数を矯正する方法ですが、日本眼科学会のガイドラインでは強度近視はレーシック適応外とされています。これは角膜を削る量が多くなりすぎ安全域を超える可能性があるためです。
強度近視の方で手術による視力回復を希望する場合、有水晶体眼内レンズ(ICL)手術が選択肢となります。ICL手術は眼内に薄いレンズを挿入して視力を矯正する方法で、角膜を削らないため-10D以上の近視でも矯正が可能です。実際、ICLは強度近視の矯正に適した手術として近年広く行われています。ただし手術にはリスクも伴うため、医師と十分相談したうえで適応を判断する必要があります。
強度近視における合併症の治療法
強度近視が原因で起こる合併症に対しては、それぞれ専門的な治療が行われます。以下に主な治療法をまとめます。
黄斑部出血(近視性脈絡膜新生血管)
黄斑部出血では、抗VEGF薬の硝子体内注射が第一選択です。月1回程度の頻度で眼球内に注射を行い、新生血管による出血や浮腫を抑えます。多くの場合この治療で視力の維持・改善が期待できます。効果不十分な場合や再発例では、光線力学的療法といって新生血管に選択的に作用するレーザー治療を併用することもあります。出血が吸収された後、黄斑部に瘢痕が残ると視力回復に限界がありますが、できるだけ早期に治療することで瘢痕化を小さくし視力予後を高めることが可能です。
近視性牽引黄斑症
網膜の構造的な問題ですので、進行して視力低下が著しい場合は硝子体手術による治療を行います。黄斑円孔や広範な網膜剥離を伴う場合も、硝子体手術を行い治療します。手術後、網膜が正常に回復すれば徐々に視力改善が得られることも多いですが、治療までの期間が長いと完全にはもとどおりにならないこともあります。早めの手術介入が視力予後を左右するため、牽引黄斑症と診断された場合は主治医と治療のタイミングをよく相談してください。
近視性視神経症
根本的な治療法はないため、進行予防が重要となります。基本は緑内障に準じた点眼治療で、眼圧が高ければ降圧剤を使い、正常眼圧でも視野進行があれば必要に応じて点眼加療を行います。点眼の効果が乏しい、あるいは進行が止まらない場合、緑内障手術を行うこともあります。残念ながら、傷んだ視神経を再生させる治療はないため、失われた視野を取り戻すことはできません。症状が初期のうちに見つかれば、その時点から治療介入して進行を遅らせ、視野の大部分を生涯維持することも十分可能です。
強度近視を防ぐためにできること

強度近視への対策でもっとも重要なのは、そもそも近視を強度になるまで進行させないこと、つまり予防です。特に子どもの頃に近視が早くから進行すると将来強度近視になる確率が高まるため、小児期からの近視進行抑制が重要となります。以下に、強度近視を防ぐために日常でできる主な対策をまとめます。
以下のような対策を継続することで、強度近視になるリスクを減らしたり、強度近視であっても重篤な合併症を未然に防いだりすることが期待できます。近視は生活習慣とも関係が深いので、日々のちょっとした心がけの積み重ねが将来の視力を守ることにつながります。
1日2時間程度の屋外活動
子どもの近視予防には、1日2時間程度の屋外遊びが有効とされています。屋外で過ごす時間が長い子ほど近視の進行が緩やかな傾向があります。
近業作業の工夫
スマートフォンや読書など近くを見る作業(近業)を長時間続けると近視が進みやすいと考えられています。子どもだけでなく大人でも、パソコンやスマートフォンを使い続ける際は30分に1回は休憩を取り、遠くを見て眼をリラックスさせましょう。
低濃度アトロピン点眼の活用
子どもの近視進行抑制には低濃度アトロピン点眼が有効です。シンガポールなどではすでに一般的な治療です。
近視進行抑制メガネ・コンタクトの利用
最近では遠近両用眼鏡や多焦点ソフトコンタクトレンズ、そしてオルソケラトロジーといった、近視抑制効果を狙った矯正器具も登場しています。
定期的な視力検査と眼科受診
近視はゆっくり進行するため、子ども自身や親御さんが気付かないうちに強度近視になっていることがあります。学校検診などで視力低下を指摘されたら放置せず眼科を受診しましょう。
まとめ

強度近視は必ずしも失明につながる状態ではなく、多くはメガネやコンタクトで日常生活を問題なく過ごすことができます。しかし、強度近視はさまざまな目の病気の原因になることがあり、それらは視力に大きな影響を与える可能性があります。そのため、そもそも強度近視にならない対策が重要です。本記事が近視に対する理解を高め、強度近視で困る方が減る一助になれば幸いです。
参考文献
