網膜剥離は特別珍しい病気ではなく、老化や近視が原因でも発症します。そして、発症して放置すると失明に直結する怖い病気です。
網膜剥離の治療は大部分が硝子体手術になります。眼球に穴を開け内部にあるゲル状の硝子体(しょうしたい)を切除して、はがれた網膜を元の位置に戻す手術です。
繊細で難易度の高い手術ですが、一般的な眼科クリニックでも局所麻酔で日帰り手術が行われています。
この記事では網膜剥離と硝子体手術に関して詳しく解説します。手術の流れや費用・メリットとデメリット・合併症・術後のケアも紹介するので参考にしてください。
網膜剥離の治療における硝子体手術

網膜剥離がおこってしまった場合、治療方法は手術が選択されます。網膜剥離の状態によって手術の方式は違ってきますが、そのうち眼球内部から行われる硝子体手術の概要を解説していきましょう。
網膜剥離とは
網膜は眼球の奥にある厚みが0.1~0.4mm程度の膜状の組織です。光を刺激として感じる機能を持ち、カメラの撮像素子(CCD)またはフィルムに相当します。
10層からなる膜で内側の9層を神経網膜といい、これが外側の網膜色素上皮細胞からはがれた状態が網膜剥離です。
初期のうちは飛蚊症(蚊が飛んでいるように見える)・光視症(視野に光が見える)程度ですが、進行すると見えない部分ができる視野欠損や視力の低下などの症状が現れ、進行して失明する場合もあります。
原因はさまざまで、代表的なものでは加齢や強い近視・外傷などです。これらの原因で網膜に裂け目ができると、そこから剥離が始まり裂孔原性網膜剥離になります。
裂孔が開かない非裂孔原性網膜剥離もあり、こちらは糖尿病など血管性の病気やぶどう膜炎などの炎症が原因です。
硝子体手術が対象となる網膜剥離の種類

硝子体手術が行われる網膜剥離では、症例が多い裂孔原性網膜剥離が挙げられます。網膜剥離といえば一般的に裂孔原性を指す程です。
また、孔が開かないタイプの非裂孔原性網膜剥離では、牽引性網膜剥離が硝子体手術の対象になります。
糖尿病や網膜静脈閉塞症で網膜周辺の毛細血管機能が低下し、新しい増殖組織や新生血管が作られます。粘着性が強い新生組織に引っ張られ、網膜がはがれる症状です。
同じ非裂孔原性網膜剥離でも、ぶどう膜炎・眼内腫瘍・網膜血管腫などが原因の滲出性網膜剥離では、手術ではなく原因になった病変が治療の対象になります。
網膜剥離に対する硝子体手術と網膜復位術の違い
網膜剥離の硝子体手術は、眼の内部から手術操作が行われます。これに対し網膜復位術では眼の周囲から圧力を加える操作で膜のはがれを治す手術です。
硝子体手術では白目部分に3~4個開けた穴から器具や照明を入れ、内部の硝子体を切除したうえではがれを修復します。
修復は眼内に注入したガスやオイルの浮力を利用して、はがれた膜を元の位置にくっつける方法です。主に50歳代以上の患者さんに適用されます。
網膜復位術はバックリング手術・強膜内陥術ともよばれます。まず剥離部分の裂孔をレーザー・冷凍などで凝固させてふさぎ、そのうえで外側にシリコン材を装着し、圧力をかけ内側にへこませて密着させる方法です。
硝子体がしっかりしている若い患者さんに多く適用されます。
硝子体手術について

硝子体手術は裂孔原性網膜剥離の約90%に適用されるほか、網膜症や加齢黄斑症・黄斑円孔・黄斑前膜など多くの症状にも適用されます。ポピュラーであっても繊細で難易度の高い手術の詳細を見ていきましょう。
硝子体手術の流れ
網膜剥離に対する硝子体手術では、基本的に局所麻酔です。麻酔後に黒目の端から3.5~4mmの部分に直径0.4~0.5mmの穴を3つ開け、照明・手術器具・潅流液注入用のチューブを差し込みます。
潅流液は器具で硝子体を細かく切りながら切除した後、代わりに内圧維持のため注入される液体で、眼内を循環する房水に近い人工液です。
裂孔から剥離部内の水分を排出し、網膜を元の位置に戻した後は裂孔をレーザーでふさぎます。眼内にガスまたは空気を入れ、浮力で網膜を奥の内面にくっつけたら手術は完了です。
入れたガスや空気は数週間のうちに吸収され、分泌された房水に置き換わります。術後は目の奥にある網膜がガスの浮力で押し上げられる状態を維持するため、しばらくはうつ伏せ状態の継続が必要です。
硝子体手術の費用
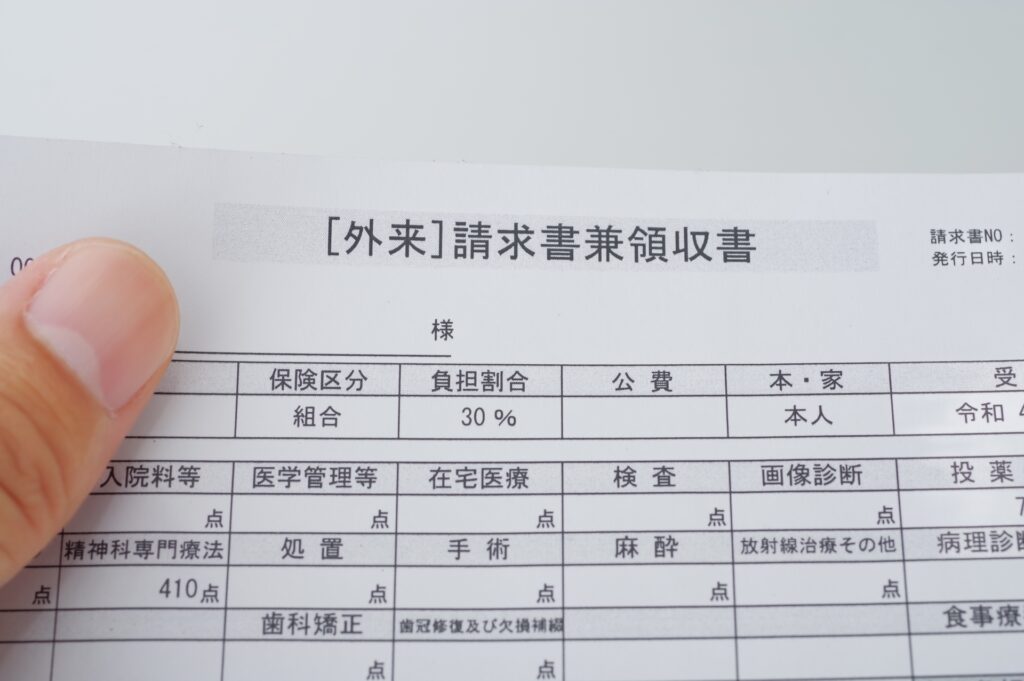
網膜剥離を治療するための硝子体手術には健康保険が適用されます。手術費用は網膜の状態によって変動するため一定ではありません。費用のうち自己負担額
は収入または年齢によって負担割合が変わり、金額の目安は以下のとおりです。
- 1割負担:30,000~60,000円
- 2割負担:60,000~120,000円
- 3割負担:90,000~180,000円
-
(※片目の金額・税込)
上記金額は日帰りの場合で、入院の場合は別途入院費が必要です。また、申請により高額療養費制度が適用されると、負担限度額と支払額との差額が後日払い戻しされます。
硝子体手術の入院期間
硝子体手術では硝子体手術で日帰り手術で行われることも多いです。しかし、網膜剥離の硝子体手術では入院する場合もあり、その場合は1~2週間程度の入院期間になります。
網膜剥離の硝子体手術では、剥離部分を固定させるためにガスやオイルが注入されます。その浮力を利用して、はがれた網膜を持ち上げて目の奥に密着させるため、術後はうつ伏せ状態での安静期間が必要です。
状態により1~2週間程度までトイレや食事以外はうつ伏せで過ごすため、日常生活に介助・手助けが必要になります。
自宅では不安な方や家族がつききりで世話できない方は、入院した方が楽に過ごせるでしょう。入院設備がないクリニックでは、提携病院へ紹介されます。
硝子体手術のメリット・デメリット

硝子体手術は失明につながる可能性がある網膜剥離を低リスクで治療できる手術で、多くの網膜剥離に対して広く適用されています。
メリット
- 局所麻酔で施術できる
- 手術創が小さい
硝子体手術では痛みが少ないため局所麻酔が基本です。眼の裏に4ml程の薬剤を注射するだけなので身体への負担が少なくてすみます。
手術では白目に小さな穴を3個開けるだけで、術後の縫合もありません。傷も残らず痛みも少なく、身体への影響がとても少ない手術です。
デメリット
- 術後に姿勢を制限される
- 場合によっては水晶体を除去する
網膜剥離で硝子体手術を受けた場合、多くの場合ガスやオイルを注入します。そうすると定着を待つ1~2週間はほとんどうつ伏せで過ごす、厳しい制約を受ける生活です。
また、白内障がある場合は医師の視野を確保して安全性が高い手術を行うため、濁った水晶体をレンズに入れ替える白内障の手術を同時に行います。ただし、この場合は白内障の治療であっても視力の向上は期待できません。
硝子体手術に伴う術後の合併症

硝子体手術に限らず手術全般に見られることに、合併症のリスクがあります。硝子体手術がきっかけで新たな障害が生じる合併症にはどのようなものがあるのか、個別に見ていきましょう。
眼内炎
硝子体手術は傷が極めて小さい手術ですが、外気に直接さらされるために、眼の表面の病原菌が侵入して感染性眼内炎を発症する可能性があります。
術前・術後に抗生剤を使い、術中にも消毒を徹底するなど予防措置を行っても、感染を完全に防ぐには至らないのが現状です。感染症の発症率は0.1%で高くはありません。
発症すると再手術や抗生剤投与で対応しますが、視力の回復は難しくなります。
駆逐性出血
駆逐性出血とは手術中や手術直後に突然発生する、上脈絡膜腔からの大出血です。眼内の動脈圧上昇・眼圧低下・疼痛を伴い、出血とともに網膜が盛り上がってきます。
さらに、眼内の虹彩・水晶体などの組織が手術の傷から出てくる場合もある症状です。眼内手術の合併症のなかでは重い症状で、血圧上昇・せき込み・緊張などがきっかけとされます。
発症率は0.4%で稀な合併症とはいえ、おこってしまうと失明に直結する重大な症状です。早期に気付いてただちに傷を閉じれば、再手術で視力が残せます。
網膜再剥離

剥離した網膜を元の位置に戻す硝子体手術後、数日~数週間後に再度剥離する場合があります。裂孔のふさぎ方が不完全であったり別の裂孔を見落としたり、新生裂孔などが原因です。
また、手術後の網膜上に新生組織ができる、増殖性硝子体網膜症が原因の場合もあります。いずれにしても再手術による対応です。
ただ、増殖性硝子体網膜症は難治性で、通常の手術に加えて強膜内陥術・輪状締結術を併用する場合があります。
さらに、眼内に注入するガスは2週間程度で吸収されるため、吸収されず長期間眼底を押さえることが可能なオイルを使います。この場合は後日抜き取りが必要です。
白内障の進行
硝子体手術の後、白内障が進行する場合があることは広く認識されています。特に50歳以上の患者さんでは79.8%程の確率で白内障の進行が報告されています。
原因として切除した硝子体に含まれていたサイトカインや酸
化反応の影響で、水晶体線維の並びが乱れて濁りが生じるといわれますが、まだ確定的ではありません。
このような状況により、硝子体手術を行う場合には白内障の手術も同時に行い、水晶体を眼内レンズに置き換えておけば白内障悪化の心配がなくなります。
現在では、硝子体手術に先立って白内障の手術を行うことが標準的です。この処置により、硝子体手術時に視野が確保されて安全性の向上が期待できます。
硝子体手術後の注意点

硝子体手術は大変デリケートです。また、手術終了後もはがれた膜を押さえ続けて安定させる治療が続きます。いろいろな術後の注意事項や指示があり、しっかり守らないと結果は期待できません。術後の注意点を詳しく解説していきましょう。
安静・体位制限が必要になる
網膜剥離の硝子体手術では、はがれた網膜を元の位置に戻し、再びはがれないようにガスやオイルの浮力を利用して目の奥方向に押し付けています。
その状態を維持するため、手術後1日から長くて2週間程度の間、うつ伏せで安静にすることが求められます。
食事とトイレ以外は就寝中もうつ伏せの姿勢を続けるため、かなり忍耐が必要です。洗顔はもちろん、入浴やシャワー・メイクなどもできません。
ひたすら安静に努め、身の回りの世話は家族の方にお願いするようになります。一人暮らしの方であれば、費用はかかりますが入院するようになるでしょう。
医師の指示通りに点眼する

手術後は3~4種類の点眼薬を毎日点眼するように指示されます。通常は朝・昼・夜・寝る前の4回ですが、状態によって増減されるので、指示にしたがって点眼してください。
手術後の眼には傷が残り、感染しやすい状態です。点眼時に雑菌が入って眼内炎などをおこさないよう、点眼前には手を洗いアルコールで消毒してください。眼の周囲も清浄綿で軽く汚れを落とします。
複数の点眼薬を使うので、次の点眼まで5分以上の間隔を開けます。点眼時には指でまぶたを触らず、下まぶたのふくらみを下に引くだけにしましょう。
また、容器の先端がまつ毛や眼球に触れないよう注意してください。点眼期間も指示されるのでそれに従い、自分の判断で中止してはいけません。
疼痛・異物感が生じる可能性がある
網膜剥離で硝子体手術をした後、痛みを感じたりゴロゴロする異物感が出たりする場合があります。数日から2週間程続き、時間の経過に伴って次第に治まる症状です。
近年では手術時に開ける孔が小さくなり、術後の縫合を省略する場合もあるので、痛みや異物感をおぼえる例は少なくなりました。
ただ、眼の状態が特殊な場合や手術中に行った処置によっては、強い痛みが出ることもあります。その場合でも鎮痛剤や眼圧を下げる点眼薬で対処が可能です。
視力回復までの期間には個人差がある
網膜剥離で硝子体手術をした直後は、注入したガスや空気の影響で大変見えにくい状態です。その後ゆっくりと回復に向かいますが、期間は個人差が大きくなります。
数ヵ月かけてゆっくり回復し、視界が安定するまでには半年から1年程かかるのが普通です。ただ、どこまで回復するかは治療前の重症度合いが大きく関与します。
網膜ははがれている間に機能が低下するものです。また、中心部の黄斑付近まではがれた場合は、視野のゆがみが残ることもあります。
元どおりに戻ることは難しいものの、それに近い視力を取り戻すには、はがれが小さいうちに診断して手術を受けることが大切な要件です。
まとめ

網膜剥離の硝子体手術に関して解説してきました。
網膜剥離はさまざまな原因でおこり、失明につながる病気にも関わらず、初期では自覚症状に乏しく早期発見しにくい病気です。
滲出性以外のほとんどの網膜剥離が硝子体手術の対象になります。硝子体手術は眼内の硝子体を切除してはがれた網膜を復位させ、膜を固定するガスや空気を注入して終了です。
術後の視力回復には長時間かかるのが特徴ですが、一般的に剥離が進んでいない早期に診断して手術を行う程回復が早く、視力の回復度合いも原状に近づけられます。
網膜剥離が進行する程治療成績が下がるため、眼の見え方に何か異変を感じたら早目に眼科で検査を受けることをおすすめします。
参考文献
