緑内障とは、主に眼圧の影響を受けて視神経が障害され、視野障害が生じる病気です。加齢により発症する可能性は高くなりますが、若くして発症する場合もあります。そのため、予防や早めの治療がとても大切です。さらに、現代の必需品ともいえるスマホが、緑内障の原因となることも考えられます。この記事では、緑内障とスマホの関係や、緑内障を予防するための、適切なスマホの使い方を解説します。緑内障について知りたい方、スマホをよく使用する方は、ぜひ参考にしてください。
緑内障の原因と症状
 緑内障とは、視野や視神経に異常が出る眼の病気です。眼圧を下げることで、症状を改善したり抑えたりできるといわれています。眼圧とは眼にかかる圧力のことで、すべての緑内障で眼圧が高いわけではありません。
緑内障とは、視野や視神経に異常が出る眼の病気です。眼圧を下げることで、症状を改善したり抑えたりできるといわれています。眼圧とは眼にかかる圧力のことで、すべての緑内障で眼圧が高いわけではありません。
緑内障は、原因がはっきりとわからない場合もあり、原因不明の緑内障を原発緑内障といいます。一方で、何らかの原因により発症したと考えられる緑内障を、続発緑内障といいます。どの緑内障でも、発症初期には自覚症状が少なく、気付かないうちに進行することも少ない病気です。
緑内障の主な原因
緑内障は、原因がはっきりしないことが少ない病気です。続発緑内障のように、発症原因が明らかな場合はあまり多くありません。ただ、緑内障のリスク要因となりうるものはたくさんあります。例えば、加齢、遺伝、生活習慣、ストレス、強い近視、眼精疲労などです。
眼精疲労を引き起こす要因として、スマホの使用は多くの方に当てはまるのではないでしょうか。長時間のスマホの使用は、眼に大きな負担をかけ、緑内障をはじめとする眼の病気につながる可能性があります。
緑内障の基本的な症状と特徴
緑内障の基本的な症状に、見える範囲が狭くなる、一部が欠けて見えなくなるなどがあります。しかし、発症初期は自覚症状がほとんどなく、症状が出たときにはすでに緑内障が進行していることも少なくありません。日本では、40歳以上の約5%が緑内障を発症しているといわれており、失明原因の第1位です。
緑内障にはさまざまな分類があり、細かく理解するのはとても難しいです。ここでは簡単に、原因による分類と隅角の形態による分類で、それぞれ分けて示しています。隅角とは、眼の中を満たしている水の出口となる部位です。眼の中の水は房水と呼ばれます。それぞれの分類ごとに特徴を確認しましょう。
原因による分類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 原発緑内障 | 原因不明の緑内障 |
| 続発緑内障 | 外傷、薬の使用、糖尿病、高血圧など、 何らかの原因により発症したと考えられる緑内障 |
| 先天緑内障 | 生まれつき発症している緑内障 生後早期に発症するものも含めて、小児緑内障と呼ばれることもある |
隅角の形態による分類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 開放隅角緑内障 | 隅角が狭いわけではないが、房水がうまく排出できない緑内障 眼圧が高くない場合もあり、正常眼圧緑内障と呼ばれる |
| 閉塞隅角緑内障 | 隅角が狭いことで房水がうまく排出できず、眼圧が上がる緑内障 一般的な風邪薬やアレルギー薬などに含まれる成分により、 悪化することがあるため、薬を飲む際は注意が必要 |
緑内障は、種類によって治療法や注意点が異なります。例えば、閉塞隅角緑内障では、避けた方がよい薬があるため、薬を飲む際は注意が必要です。もし緑内障と診断されたら、どの種類の緑内障なのか、眼科医にしっかりと確認しましょう。
若年層でも発症する緑内障とは
加齢は緑内障の主な原因のひとつですが、20代や30代などの若年層でも緑内障を発症することがあります。若年層で発症する緑内障の原因として、スマホの使用や、生活習慣の乱れなどが挙げられます。
長時間スマホを使用する方、糖尿病や高血圧などの生活習慣病を患っている方、睡眠不足が続いている方は注意が必要です。当てはまる方は、緑内障を発症するリスクが高いといえるので、しっかりと対策しましょう。
スマホ使用が眼に与える影響
 スマホは現代において必需品といえるでしょう。しかし、使い方によっては眼に多くの悪影響を及ぼす可能性があります。特に、長時間の使用による影響、ブルーライトによる影響、近距離での使用による影響が懸念されます。
スマホは現代において必需品といえるでしょう。しかし、使い方によっては眼に多くの悪影響を及ぼす可能性があります。特に、長時間の使用による影響、ブルーライトによる影響、近距離での使用による影響が懸念されます。
どれかひとつではなく、複数の要因が重なることで、緑内障のリスクがさらに高まることもあるでしょう。ここからは、それぞれの影響について具体的に解説します。ぜひスマホの使用方法について考えるきっかけにしてください。
長時間のスマホ使用が眼に与える影響
スマホを使用する場合、多くの方は手に持って使用することでしょう。長時間スマホを使用すると、ずっと同じ距離に焦点を合わせている状態になります。すると、ピントを調節する眼の筋肉が疲れて硬直します。眼の筋肉が硬直すると、ピントを調節しにくくなり、眼精疲労や視力低下につながるのです。
スマホの使用により、姿勢が悪くなることも考えられます。長時間悪い姿勢でスマホを使用すると、血流が悪くなったり、眼圧が上がったりします。血流悪化や眼圧上昇により、緑内障が悪化する可能性があるため注意が必要です。さらに、スマホに集中しているとまばたきの回数が減り、ドライアイになるリスクも上がります。ドライアイにより、眼に傷がついたり疲れたりする原因になり、悪循環となります。
ブルーライトによる影響
ブルーライトとは、スマホなどから出ている光の一種です。ブルーライトは、刺激として直接眼にダメージを与えるだけでなく、眼の疲れや痛みなどを引き起こす原因にもなります。また、ブルーライトは太陽光にも含まれる光の一種です。
普段私たちは、太陽光を浴びて、身体が日中だと認識して活動しています。特に、夜のスマホ使用がよくないといわれるのは、夜でも日中だと身体が勘違いして眠りにくくなり、睡眠の質が下がるためです。睡眠不足が続くと、緑内障の発症や悪化につながる可能性があります。
近距離でのスマホ操作が引き起こす問題
スマホを使用する際は、眼とスマホの距離にも注意しなければいけません。眼とスマホの距離が近いと、眼に入るブルーライトの量が多くなり、影響も大きくなるといえます。それだけでなく、近くの物を見るために寄り目の状態が続くことも大きな問題です。
近距離でスマホを見る状態が長時間続くと、眼の筋肉の硬直により、寄り目の状態から戻らなくなることがあります。寄り目の状態が続くことを内斜視といいます。内斜視になると、視力が落ちたり、物が二重に見えたりしてとても危険です。
緑内障を予防するスマホとの付き合い方
スマホの使用が緑内障の原因になる可能性があるとしても、スマホをまったく使用しないのは難しいでしょう。そのため、使用時間や使用方法を見直し、スマホとの付き合い方を考える必要があります。緑内障予防の観点から、スマホをどのように使用するのがよいのか紹介します。ぜひ参考にしてください。
スマホ使用時に実践すべきルール
あらかじめルールを決めておくことで、できるだけ眼に負担がかからないように、スマホを使用できます。以下の点に注意して、スマホを使用することをおすすめします。
・1日のスマホ使用時間を決めておく
・30分ごとに休憩する
・意識的にまばたきをする
・ブルーライトの対策を行う
・眼とスマホ画面の距離を離して使用する
・就寝前にはスマホを使用しない
これらのルールを実践することで、スマホによる眼への影響を軽減でき、緑内障の予防に役立つでしょう。スマホの使用時間は、何時間までならよいという明確な決まりはありません。少しずつでもいいので、今の使用時間からできるだけ減らしていきましょう。
ブルーライト対策
スマホのブルーライトは、対策により眼への負担を軽減できます。ブルーライトをカットできるスマホの保護フィルムやメガネなどがありますので、試してみるとよいでしょう。また、画面の明るさを落とすだけでも効果があるといわれています。
スマホの種類によっては、ナイトモードなどの明るさを抑えてくれるモードが選べます。夜だけナイトモードに設定するのもひとつの手段です。
スマホ画面との距離を保つ
眼とスマホ画面の距離を保つことで、眼に入るブルーライトの量を減らせて、内斜視を予防できます。具体的には、眼とスマホ画面の距離を30cm以上離すとよいといわれています。また、スマホ画面を眼から離すのと同時に、猫背などの悪い姿勢にならないよう、意識するとよいでしょう。
就寝前にスマホの使用を控える
就寝前にスマホを使用すると、ブルーライトの影響で眠りにくくなり、睡眠の質も悪くなります。特に暗いところでスマホを使用するのは、眼に大きな負担がかかるので控えましょう。暗いところでは、眼はより多くの光を取り入れようと瞳孔を開くため、ブルーライトが眼に入りやすくなります。
また、寝転がった状態や、うつ伏せの状態でスマホを使用するのも要注意です。眼球が圧迫されることで、眼圧上昇、血流悪化、視力低下などの可能性があります。また、近視の方は特に、就寝前は眼とスマホの距離が近くなりがちになります。なぜなら、就寝前はコンタクトやメガネを外していることが多く、眼にスマホを近づけないと見えないためです。
睡眠の質を保つために、就寝の1時間前からスマホは触らないようにしましょう。
緑内障予防のためにできること
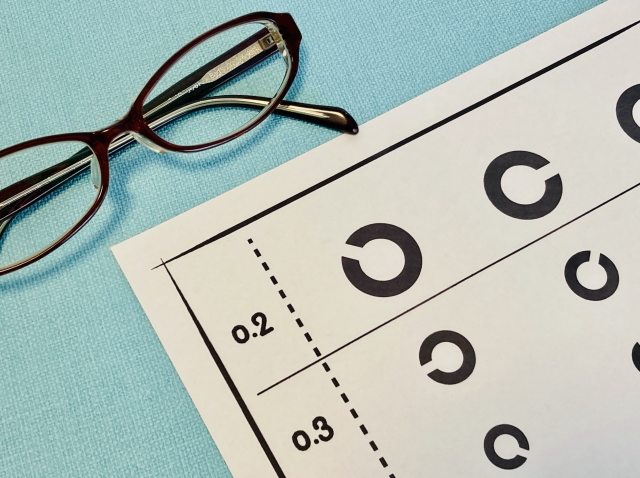 スマホの使い方を見直す以外にも、緑内障予防のためにできることはあります。緑内障予防には、日々の生活習慣に気を配ることがとても大切です。例えば、バランスのとれた食事や適度な運動、ストレスの軽減などが効果的です。
スマホの使い方を見直す以外にも、緑内障予防のためにできることはあります。緑内障予防には、日々の生活習慣に気を配ることがとても大切です。例えば、バランスのとれた食事や適度な運動、ストレスの軽減などが効果的です。
ここからは、スマホとの付き合い方以外に、緑内障予防のために役立つと考えられる具体的な方法をご紹介します。これらを実践することで、眼の負担を軽減し、健康な眼を長く保ちましょう。
定期的な眼科検診を受ける
緑内障により、一度狭くなった視野はもとには戻りません。そのため、早期発見、早期治療がとても大切です。早期発見のためには、定期的な眼科検診が欠かせません。特に40歳以上の方や家族が緑内障を患っている方は、リスクが高まるため注意が必要です。
緑内障は発症初期では自覚症状がほとんどなく、気付かないうちに症状が進行していることがあります。そのため、視力や眼圧をチェックする検査を定期的に受けることが大切です。また、早期発見により治療の選択肢が広がり、進行を抑えられる可能性が高まります。少しでも違和感があればすぐに受診し、症状がなくても定期的な受診を欠かさないようにしましょう。
バランスのよい食事を取る
眼の健康を維持し、緑内障を予防するためには、栄養バランスのよい食事が大切です。特に、ビタミンA、C、Eなどのビタミン類は、眼によいといわれています。また、緑色の葉野菜に含まれる成分が、原発開放隅角緑内障の発症リスクを抑えるという研究結果も報告されています。
ただし、これさえ食べれば大丈夫というものはなく、いろいろな栄養素をバランスよく取ることを意識しましょう。また、バランスのよい食事を取ることで、緑内障のリスク要因である糖尿病や高血圧の予防にもつながります。
睡眠不足を解消して眼の負担を軽減する
睡眠不足の状態では、眼の疲れが十分に取れず、血流低下や眼圧上昇が起きやすくなります。睡眠の質を上げるためには、毎日の睡眠サイクルを整えることがとても大切です。まずは朝起きてすぐに朝日を浴び、身体を目覚めさせましょう。日中の適度な運動もよい睡眠につながります。
入浴のタイミングは、寝る1〜2時間前がよいとされています。寝る前は徐々に部屋を暗くし、眠りやすい環境を整えましょう。適切な睡眠時間は、一般的に6〜8時間程度だといわれています。年齢を重ねるごとに、必要な睡眠時間は短くなることが多く、個人差もあります。自分に合った睡眠サイクルを見つけ、質のよい睡眠をとることで、眼に負担をかけない生活をしましょう。
運動習慣を取り入れて全身の健康を保つ
適度な運動は全身の血流を促進し、緑内障の予防にも役立つといわれています。運動によって血流が改善されると、眼への酸素や栄養の供給がスムーズになり、眼圧の安定につながると考えられます。特にウォーキングや軽めのジョギング、ヨガなどの軽度から中程度の運動が推奨されており、無理なく継続できるものを選ぶのが大切です。 バランスのよい食事と同様に、緑内障のリスク要因である糖尿病や高血圧の予防にもつながります。ただし、過度な運動や筋トレは、眼圧が上がる可能性があるので注意しましょう。毎日少しだけ歩く時間を増やす、休日に軽い運動を取り入れるなど、できることから始めてみましょう。
ストレスを軽減する生活を心がける
ストレスが慢性化すると、自律神経の乱れから血流が悪化し、眼圧が上がる可能性があります。そのため、ストレスも緑内障のリスク要因といえるでしょう。ストレスを軽減するためには、適度な運動や趣味の時間を持つことが大切です。
また、深呼吸や瞑想、軽いストレッチなど、リラックスできる時間を作るのもよいでしょう。ホットタオルで眼を温めるなど、定期的に眼を休めるのも効果的です。仕事や家事の合間に短い休憩を取り、心身の疲れをためないよう心がけましょう。自分に合ったリフレッシュ方法でストレスを軽減することが、緑内障の予防につながります。
まとめ
 緑内障は、視神経の異常や視野狭窄などが起こる病気です。スマホの使用が発症原因のひとつになる可能性があります。しかし、スマホの適切な使用を心がけ、食事や運動、睡眠などの生活習慣を改善することで、緑内障の予防や進行抑制が期待できます。
緑内障は、視神経の異常や視野狭窄などが起こる病気です。スマホの使用が発症原因のひとつになる可能性があります。しかし、スマホの適切な使用を心がけ、食事や運動、睡眠などの生活習慣を改善することで、緑内障の予防や進行抑制が期待できます。
特に日常生活で使用頻度の高いスマホの使い方を見直すことは、大きな意味があるでしょう。また、定期的に眼科検診を受けることで、もし発症しても早期に発見して治療を開始できます。スマホと適切に付き合いながら、健康的な生活を送ることで、大切な眼の健康を守りましょう。
参考文献
