糖尿病の患者さんの中には、将来、目が見えなくなってしまうのではないかと、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
糖尿病網膜症の多くは自覚症状がないまま進行し、気付いた頃には視力が大きく損なわれてしまうことがあります。
この記事では、糖尿病網膜症がどのように進行し、なぜ失明するのか、進行を防ぐために今できる対策や予防法などについて、詳しく解説します。未来の視力を守るために、正しい知識を一緒に確認しましょう。
糖尿病網膜症の概要

糖尿病網膜症は、糖尿病が進行することで生じる目の病気で、糖尿病の三大合併症のひとつに数えられます。成人における失明原因として、上位に挙げられる重要な疾患です。
血糖値の変動が大きかったり、高血糖が続いたりすると、血管の壁が傷つき、全身で血管の合併症が進行します。眼においても同様で、糖尿病網膜症が進行すると、眼の一番内側の膜である網膜に、血流が行きわたらなくなります。血流にのって供給されるはずだった酸素の不足を補うために、細い血管が新たに作られますが、これによってさまざまな病態が引き起こされ、視力が低下します。
糖尿病網膜症の初期段階では症状が出にくく、ほとんどの方では自覚症状がないまま進行していきます。このため、糖尿病のある方は、定期的な眼科検診が強く推奨されています。特に眼底検査では、網膜の血管の状態などを詳しく調べることができ、早期に異常を発見できる可能性があります。
糖尿病網膜症の自覚症状が現れる頃には、病気が進行していることも多く、治療が難しくなる場合があります。そのため、早期発見と適切な治療が大変重要です。進行を抑えることができれば、失明のリスクを大きく減らせる可能性があるため、定期的に眼科を受診しましょう。
糖尿病網膜症で失明する理由

糖尿病網膜症で失明する主な理由としては、大きく次の4つが挙げられます。
- 硝子体(しょうしたい)出血
- 網膜剥離(はくり)
- 黄斑(おうはん)浮腫
- 血管新生緑内障
これらの異常は、糖尿病網膜症の進行によって生じます。糖尿病網膜症が進むと、眼の中の血管が詰まりやすくなります。このため、眼の一番内側にある網膜と呼ばれる膜への血流が悪くなります。それを補おうとして異常な血管が新たに増え、さまざまな合併症を引き起こすのです。ここからは、それぞれの仕組みを順に解説します。
硝子体出血
眼球の中は、硝子体と呼ばれるゼリー状のもので満たされています。硝子体はもともと透明ですが、そこに出血が起こってしまうと、濁りによって視力が低下してしまうことがあります。
網膜剥離
眼球の壁はいくつかの膜で形成されており、一番内側にある膜を網膜と呼びます。これはカメラでいうところの、フィルムの役割を果たします。
通常、網膜は眼球の壁にぴったりと張り付いています。糖尿病網膜症が進行し新しい血管が作られると、その周囲に増殖膜と呼ばれる膜ができます。この増殖膜が網膜を引っ張ることで、網膜がはがれてしまうことがあります。これを網膜剥離といいます。発症時には、視界に虫やゴミが飛ぶ、飛蚊症などの症状や視野が欠けてくる視野欠損など、はっきりとした症状が現れるのが一般的です。
黄斑浮腫
網膜の中心部のことを黄斑といいます。物を見るために重要な細胞がたくさん集まっている部分で、黄斑はものを見るために特に大切な場所です。糖尿病ではこの黄斑がむくんでしまい、眼のかすみなどの視力低下につながります。
血管新生緑内障
眼の中では、房水(ぼうすい)と呼ばれる水が循環し、水晶体や角膜の表面などを洗う役割を果たしています。
糖尿病網膜症が進行し、新たな血管が作られるようになると、房水が目の外へ流れ出す部分にも、血管が形成されることがあります。これにより、房水の排出が妨げられてしまい、眼の中に房水がたまってしまいます。すると、眼の中の圧が上がり、ものを見るための神経(視神経)を圧迫して、緑内障の状態になってしまうことがあります。
血管新生緑内障は治療が難しく、失明に至る可能性が高い病気です。
糖尿病網膜症の進行段階

糖尿病網膜症は大きく3つの進行段階があります。ここでは順番に進行段階を説明します。
単純網膜症
糖尿病網膜症の初期段階を単純網膜症といいます。この時期には、細い血管の壁が膨らんでできる血管の瘤や、小さな出血といった異常がみられます。また、血管から蛋白質や脂肪が漏れ出して、網膜に付着しシミのようなもの(硬性白斑)を形成することがあります。
この時期には自覚症状がみられないことがほとんどです。眼底の検査で今挙げたような異常が見られた場合、単純網膜症の進行が始まっているサインです。ただ、これらの異常は血糖値のコントロールがよくなれば、改善することもあります。
増殖前網膜症
単純網膜症が進むと、増殖前網膜症という段階になります。血管の障害が進行することで、細い血管が閉塞してしまい、網膜への血流が途絶えます。これにより、網膜への酸素の供給が不足し、これを補うために新しい血管を作る準備を始めます。
この時期になると、かすみなどの自覚症状がでることが多いとされています。
増殖網膜症
増殖前網膜症からさらに病状が進行すると、増殖網膜症と呼ばれる重症の段階に入ります。網膜の酸素不足を補うための新たな血管が作られるのです。新生血管と呼ばれるこの血管は、網膜や硝子体に向かって伸びていきます。増殖網膜症の段階になると、血糖値の状態に関わらず病状は進行し、視力低下が進み失明の状態になることがあります。
この時期には硝子体出血や網膜剥離が生じやすくなります。
糖尿病網膜症の進行サイン
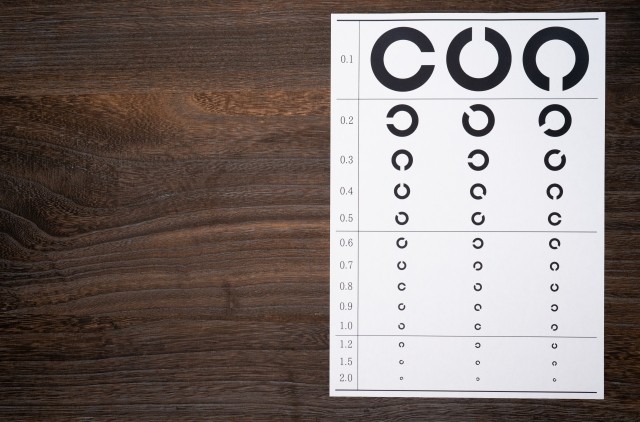
糖尿病網膜症が進行すると、以下の症状が見られることがあります。
霧視(むし)
霧視とは、目が霧のようにかすんで見える状態を指します。霧視にはさまざまな原因があり、糖尿病網膜症もそのうちの一つです。
飛蚊症(ひぶんしょう)
黒い虫やゴミのようなものが目の前に見える、飛蚊症という症状がみられることがあります。これは、糖尿病網膜症において、硝子体出血や網膜剥離が原因の可能性があります。
急激な視力低下
糖尿病網膜症が進行すると、突然文字が読みにくくなったり、遠くの景色が見えにくくなるなどの、急激な視力の低下がみられることがあります。硝子体出血や網膜剥離の可能性があります。
目の痛み
眼圧が上がると目の痛みや充血などの症状が出ます。また、目が痛いほどの眼圧になると、視野の一部が欠けたり、視力が大きく下がる恐れがあります。
糖尿病網膜症による失明を防ぐには

血糖コントロール
糖尿病網膜症の進行を防ぐためには、まず血糖値を適正に管理することが重要です。単純網膜症の段階では、血糖コントロールを良好にすることで、糖尿病網膜症がない状態に戻ることがあります。また、網膜症の進行を遅らせることにもつながるため、失明のリスクを下げることができます。
ただし、急激に血糖値を下げると、一時的に網膜症が悪くなる可能性があるため、すでに網膜症を発症している方は注意が必要です。血糖コントロールについては、必ず主治医と相談しながら進めるようにしましょう。
血圧コントロール
高血圧そのものも、網膜に病変を引き起こすことがあります。さらに、高血圧は糖尿病網膜症を悪化させる可能性も指摘されており、適切な血圧管理が網膜症の発症と重症化の予防につながります。
レーザー治療
糖尿病網膜症の治療として、網膜光凝固術があります。これはレーザーの光で、眼底の悪くなった部分を焼く治療です。新生血管を焼くことで、そこから出血するのを予防したり、新生血管が出てくるのを予防したりします。
点眼による麻酔だけで行えるため、外来通院で治療ができます。ただし、この治療は予防治療であり、視力が改善するわけではありません。しかし、将来の視力悪化を防ぐために重要な治療法です。
硝子体手術
硝子体出血や網膜剥離が起こった場合、硝子体手術が行われることがあります。目の中の出血を取り除き、出血の原因となる部分を焼いて止血し、剥離した網膜を元に戻します。
糖尿病網膜症の進行をおさえる生活習慣

食事療法で(血糖)血圧・脂質管理
糖尿病網膜症の進行を防ぐためには、食事療法がとても重要です。血糖値だけでなく、血圧や脂質を良好に管理することが、血管の障害を抑える鍵となります。食事療法のポイントについて詳しく解説していきます。
適切なエネルギーを摂取する
1日に必要な摂取エネルギーは、年齢、性別、身長、体重、活動量によって、一人ひとり違います。太り過ぎたり、痩せすぎたりしないよう、適切な体重を目標に、必要なエネルギー量の食事を摂りましょう。
食事の塩分を減らす(減塩)
高血圧は網膜症を悪化させる原因の一つです。高血圧のある方は1日6g未満の塩分摂取を目標にしましょう。高血圧がない方も、高血圧の予防のため食事の塩分を減らすことが推奨されています。男性では1日7.5g未満、女性では1日6.5g未満です。
バランスのよい食事を心がける
主食・主菜・副菜をそろえ、野菜、海藻、きのこ類などを多く取り入れることがすすめられています。野菜、海藻、きのこ類は食物繊維を豊富に含んでおり、食事で満足感を得ることにつながります。さらに血糖値の上昇を緩やかにしたり、腸内環境を改善したりする働きがあります。
また、食後の血糖値の上昇を抑えるためには、ゆっくり食べることや、野菜やたんぱく質を多く含む食品を先に食べるなどの工夫も有効とされています。
脂質の量と質に注意する
炭水化物とたんぱく質以外のエネルギーを脂肪から摂取します。一方で、脂質の摂取量は多くなり過ぎないように(食事の20~25%)推奨されており、また、その質に注意することが大切です。
飽和脂肪酸を控え、不飽和脂肪酸を多く含む食品を摂るとよいとされています。具体的には、肉類やバターの摂取は控えめにし、魚やナッツ、オリーブオイルなどを適度に取り入れるとよいでしょう。
運動習慣で血糖・血圧・血流を改善
適度な運動はインスリンの働きを助け、血糖値を下げるだけでなく、血圧や脂質のコントロールを改善することにも効果があります。また、手足などの血流が改善されることにもつながります。
糖尿病の方の運動療法は、有酸素運動とレジスタンス運動の二つがあり、それぞれ解説していきます。
有酸素運動
有酸素運動とは、散歩、ジョギング、自転車エルゴメーター、水泳など、全身の筋肉を使い、ゆっくりと呼吸をしながら行う運動のことです。運動の前後にはストレッチなどを行いましょう。また、足に負担がかからないよう、底の厚いスポーツシューズを着用することも推奨されています。
レジスタンス運動
レジスタンス運動とは、筋肉に抵抗(レジスタンス)をかけて行うトレーニングのことです。いわゆる筋トレにあたります。全身の筋肉を使った筋力トレーニングを、週2~3回以上行うことで、筋肉量が増え筋力の強化が期待されます。
ただし、いずれの場合も、最初は軽い運動から始め、徐々に時間と強度を増やしていくことが推奨されています。糖尿病の治療で血糖を下げる薬やインスリンを使用している方、その他の合併症をお持ちの方は、特に注意が必要です。また、糖尿病網膜症がある場合、息をこらえるような運動や、身体に衝撃がある運動は避ける必要があるため、運動療法についても、主治医と相談しながら進めていきましょう。
レジスタンス運動と有酸素運動を組み合わせることも効果的とされています。自分に合った運動療法を適切に行うことで、糖尿病網膜症の進行を遅らせることにつながります。
家族や周囲ができるサポート

糖尿病網膜症の進行を防ぐために家族や周囲ができるサポートとして、定期検査と治療継続の後押しと、医療機関との情報共有があります。
定期検査と治療継続の後押し
糖尿病網膜症は、本人に自覚症状がほとんどないまま進行することがあるため、周囲の協力による定期的な眼科受診の後押しがとても重要です。特に高齢の方や視力低下のある方の場合は、通院のサポートが必要となります。
また、本人が自主的に取り組めるよう声かけしたり、血糖コントロールの重要性や、食事、運動療法への取り組みを一緒に理解し、協力することが治療の継続にもつながります。
医療機関との情報共有
糖尿病網膜症の治療には、眼科と糖尿病内科をはじめとした多くの科、そして多くの職種の連携が欠かせません。診察時の情報の共有が、より適切な診療につながります。患者さんやそのご家族は、ほかの科やほかの病院を受診した際は、必ず眼科の主治医に経過を報告しましょう。お薬手帳を毎回持参するのも大切です。
まとめ

糖尿病網膜症は、早期発見と早期治療が鍵となります。日々の血糖コントロールや、適切な生活習慣の維持、定期的な眼科受診が進行を遅らせることにつながります。そして、失明のリスクを軽減できる可能性があります。
糖尿病網膜症は自覚症状がないことが多いため、なかなか受診をされない方も少なくありません。しかし、症状が出てからでは病状が進行してしまっている可能性が高いのです。未来の視力を守るためにも、定期的に医療機関を受診しましょう。
参考文献
- 日本眼科学会, 目の病気 糖尿病網膜症
- 東京女子医科大学眼科教授 堀 貞夫, 糖尿病で失明しないために, 日本眼科医会
- Sonia Mehta, MD, (2022年4月), 糖尿病網膜症, MSDマニュアル プロフェッショナル版.
- 中村 春香, (2025.03.12), 血管新生緑内障, 社会福祉法人恩腸財団 済生会.
- 瀬口 次郎, (2019.02.27), 硝子体出血, 社会福祉法人恩腸財団 済生会.
- 糖尿病診療ガイドライン2024
- 食事療法に関する委員会(編), (2024年3月25日), 健康食スタートブック, 一般社団法人日本糖尿病学会
- 石垣 泰, 糖尿病における脂質異常症管理, 日本内科学会雑誌,2023, 112 巻 2 号(pp.181~187).
