年齢を重ねると、視界に変化を感じる場面が増えてきます。最近、ものがかすんで見える、光がまぶしい、色の見え方が以前と違う、そのような症状に心あたりがある方も多いのではないでしょうか。それは、白内障のサインかもしれません。
この記事では、「白内障は何歳から発症しやすいの?」という疑問をベースに、白内障が起こる原因や主な症状、治療の流れ、手術後の注意点までを幅広く解説します。
白内障は何歳から発症しやすい?
 白内障とは、目のなかにある水晶体(すいしょうたい)という透明なレンズが、白く濁ってくる病気です。水晶体が濁ると、カメラのレンズに曇りが生じたように、ものがかすんで見えたり、まぶしさを感じやすくなったりします。
白内障とは、目のなかにある水晶体(すいしょうたい)という透明なレンズが、白く濁ってくる病気です。水晶体が濁ると、カメラのレンズに曇りが生じたように、ものがかすんで見えたり、まぶしさを感じやすくなったりします。
白内障は年齢とともに発症しやすく、一般的には40代頃から症状が現れ始め、60代では多くの人に見られるようになります。さらに80代になると、ほぼ全員が白内障になっているとされています。
ただし、発症の時期には個人差があり、生活習慣や目への負担などの影響で、もっと若い年齢でも白内障を発症することがあります。白内障は誰にでも起こりうる、加齢とともに進行する目の変化のひとつといえるでしょう。
白内障の原因
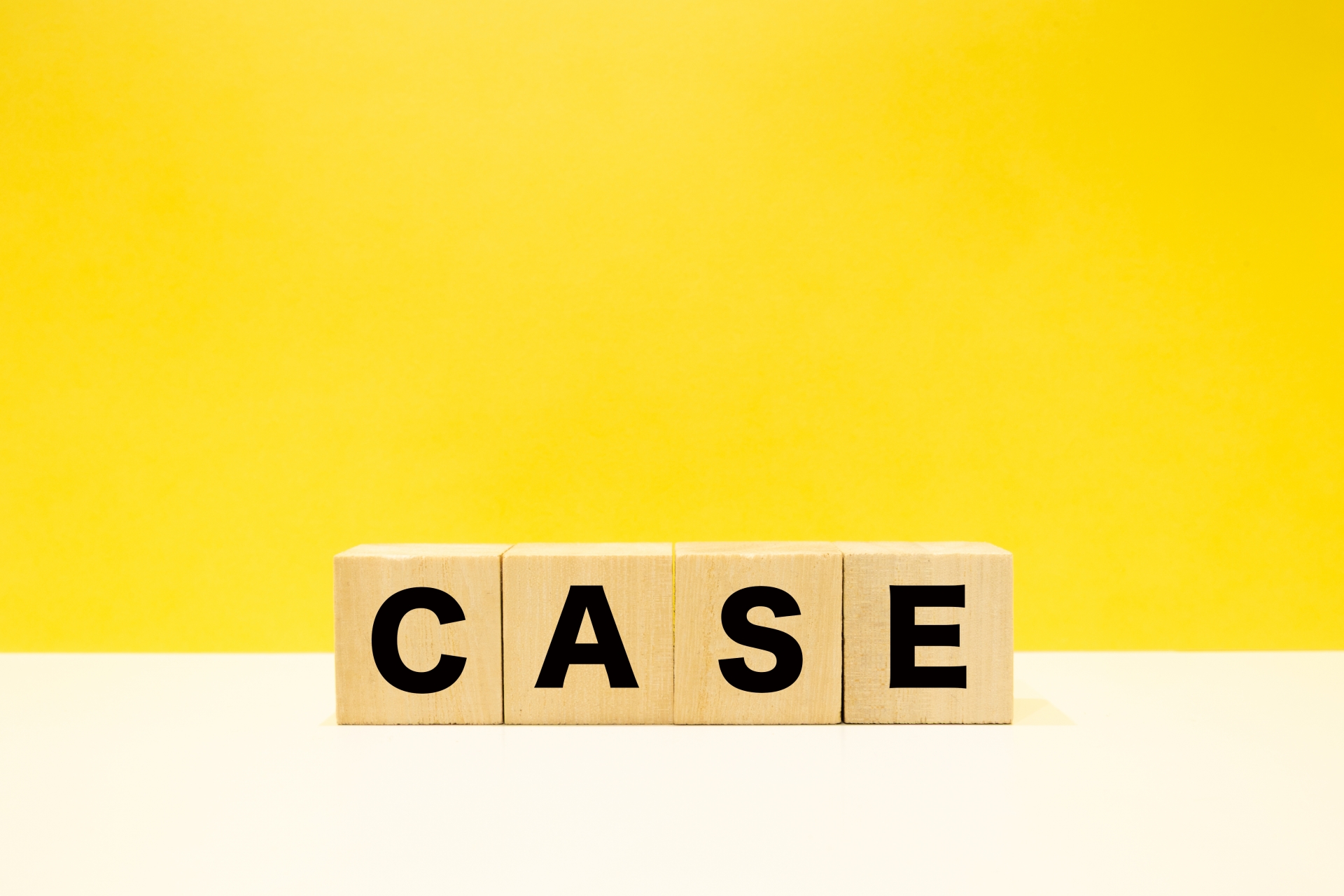 白内障は、加齢による自然な変化が多い原因ですが、それ以外にもさまざまな要因で起こります。ここでは代表的な原因を紹介します。
白内障は、加齢による自然な変化が多い原因ですが、それ以外にもさまざまな要因で起こります。ここでは代表的な原因を紹介します。
加齢
特に多い原因とされているのが加齢です。水晶体のたんぱく質成分が年とともに変化・変性し、水晶体が濁りやすくなります。これは白髪やしわと同じく、加齢に伴う自然な変化といえるでしょう。
糖尿病など全身疾患による代謝異常
糖尿病があると、血液中の余分な糖が水晶体に影響し、白く濁りやすくなります。実際、糖尿病の患者さんは健常者と比べて白内障になるリスクが約5倍高く、進行も早いとされています。
遺伝的要因
一卵性双生児を対象とした研究では、白内障の進行速度に遺伝が関係していることが示唆されています。また、家族に先天性白内障の例がある場合、若年で発症するリスクが高くなるため、注意が必要です。
紫外線の影響
太陽の紫外線を浴びることで、水晶体の酸化ストレスが高まり、白内障の発症や進行を促す要因となります。特に屋外での活動が多い人は注意が必要で、サングラスや帽子で紫外線対策をすることが推奨されます。
目のケガや炎症によるもの
強い衝撃や打撲で水晶体を覆う袋(嚢:のう)が傷つくと、白内障を発症することがあります。また、ぶどう膜炎などの目の炎症がきっかけで白内障になる場合もあります。
ステロイド薬の長期使用
ステロイド剤には目薬や塗り薬、内服薬、吸入薬などさまざまな種類がありますが、なかでも全身疾患や喘息の治療に使われる内服薬や吸入薬によって白内障を発症するケースが多く報告されています。ステロイドによる白内障は、発症後に速いスピードで進行することがあります。
白内障の症状
 白内障が進行すると、視界にさまざまな変化があらわれます。初期段階では気付きにくいこともありますが、症状が進むにつれて日常生活に支障をきたすようになることもあります。
白内障が進行すると、視界にさまざまな変化があらわれます。初期段階では気付きにくいこともありますが、症状が進むにつれて日常生活に支障をきたすようになることもあります。
視界のかすみや光のにじみ
白内障の代表的な症状のひとつが、視界のかすみです。水晶体が白く濁ることで、光がきちんと目の奥まで届かず、全体がぼんやりと曇って見えるようになります。
また、光がにじんで見えることもあり、夜間の街灯や車のライトが輪のように広がって見えるハロー現象や、まぶしさを強く感じるグレア現象が起こることもあります。 特に夜間や逆光時には、視界のにじみやまぶしさが顕著になりやすく、運転や外出に不便を感じることもあります。
まぶしさや視力の低下
白内障が進むと、光をまっすぐ通せなくなるため、日中の強い日差しや夜のライトなどに対して、これまで以上にまぶしさを感じるようになります。まぶしさの影響で目を細めることが増えたり、見たいものが一瞬見えなくなったりといったこともあるでしょう。
また、水晶体の濁りによって焦点が合いにくくなり、視力がゆるやかに低下していきます。本を読むときにピントが合いづらくなる、顔や看板がはっきり見えなくなるといった変化が見られることもあります。
二重視や色の識別変化
白内障の進行により、視界が二重に見えるような違和感を覚えることもあります。これは単眼複視といって、片目で見ているにも関わらず、像がずれて見える状態です。水晶体の濁り方に偏りがある場合に起こりやすいとされます。
さらに、色の見え方にも変化が生じることがあります。例えば、白や青などの淡い色がくすんで見えたり、全体的に黄色みがかって見えたりするようになることがあります。色のコントラストも低下し、物の輪郭がはっきりしないと感じることもあるでしょう。
白内障の種類
 白内障には発症原因や時期によっていくつかの種類があり、それぞれ症状や治療の進め方に違いがあります。ここでは主に4つのタイプをご紹介します。
白内障には発症原因や時期によっていくつかの種類があり、それぞれ症状や治療の進め方に違いがあります。ここでは主に4つのタイプをご紹介します。
加齢性白内障
加齢性白内障はとても多いタイプで、白内障の患者さん全体の約90%を占めるとされています。
上述したとおり、年齢を重ねるにつれて水晶体のたんぱく質が酸化・変性し、次第に濁りが生じるのです。多くは40代以降に少しずつ症状が始まり、50代で約半数、70代以降にはほとんどの人に濁りが見られます。
濁る部位により、皮質白内障や核白内障、後嚢下白内障などに細かく分けられますが、いずれも進行は緩やかで、生活に支障が出る頃には手術を検討する段階になります。
糖尿病性白内障
糖尿病性白内障は、慢性的な高血糖の影響により水晶体内でソルビトールなどが増え、濁りが早く進行しやすいのが特徴です。
特に後嚢部(レンズの後ろ側)に濁りが出やすく、視力やまぶしさが早期から現れることがあります。20~30代と若い世代でも発症することがあり、早期に眼科での定期チェックが重要です。
外傷性・放射線性白内障
外傷性白内障は、スポーツや事故などで目に強い衝撃を受けた場合に発症します。衝撃後すぐに濁るケースもあれば、数年後に急に症状が現れる場合もあります。
一方、放射線性白内障は、放射線治療や被曝が原因で、数ヶ月から数年後に幅広く濁りが進む可能性があります。いずれも急激に視界が悪化する傾向があるため、眼科での早急な対応が必要です。
先天性・若年性白内障
先天性白内障は、胎児期に遺伝や母体の感染(風疹など)が原因で起こるもので、生まれた時から水晶体が濁っていることがあります。視力の発達に影響を及ぼすため、出生後なるべく早期に手術が検討されることが多いです。
一方の若年性白内障は、10~30代で発症しうるタイプで、原因は糖尿病、紫外線、アトピー性皮膚炎、ストレス、薬剤など多岐にわたり、進行の速さもさまざまです。
白内障治療の流れ
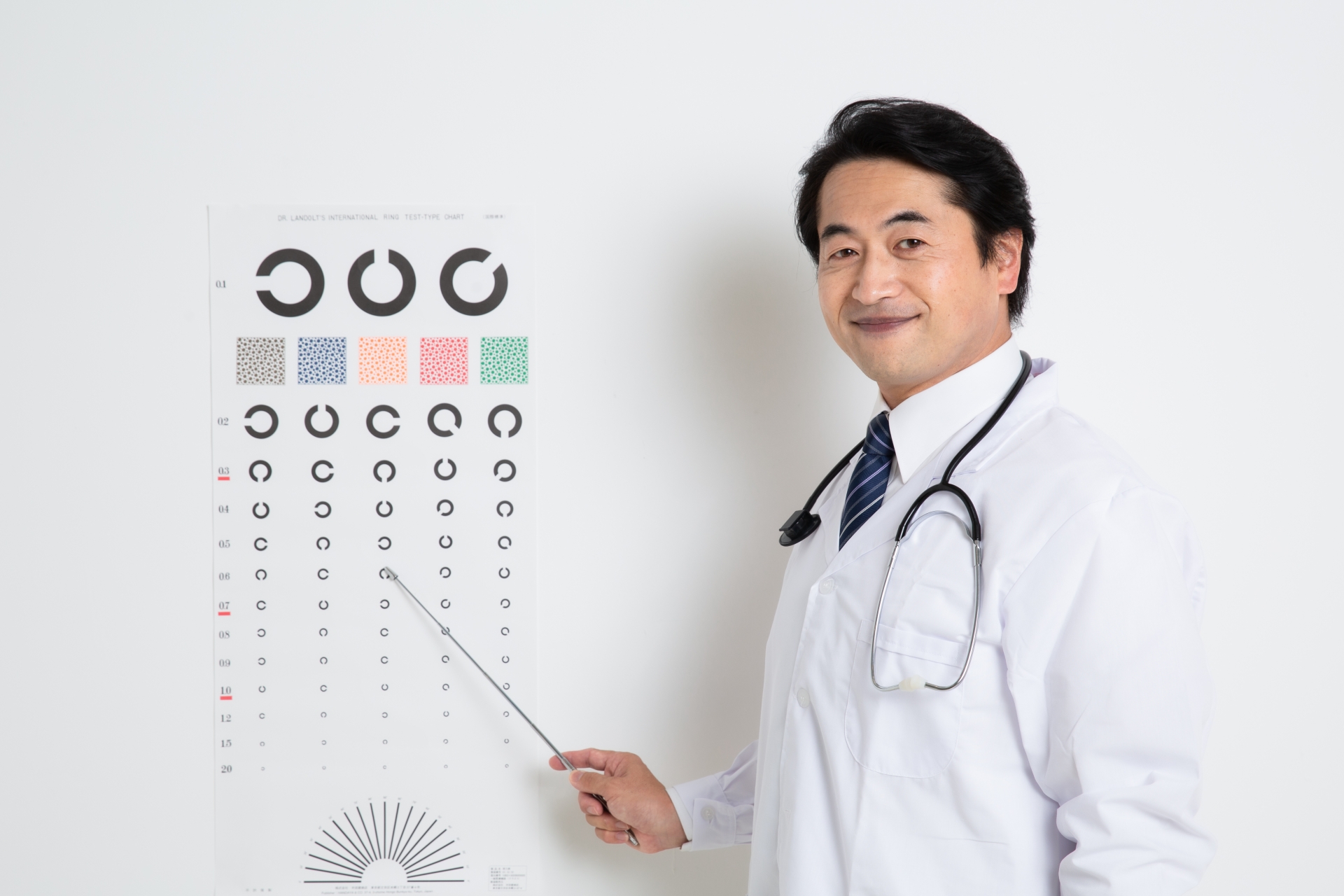 白内障の治療は、大きく分けて点眼薬による進行抑制と手術による根本治療の2つがあります。どちらの方法を選ぶかは、白内障の進行具合や生活への影響、患者さんの年齢や健康状態などを総合的に考慮して判断されます。
白内障の治療は、大きく分けて点眼薬による進行抑制と手術による根本治療の2つがあります。どちらの方法を選ぶかは、白内障の進行具合や生活への影響、患者さんの年齢や健康状態などを総合的に考慮して判断されます。
初期の場合
初期の白内障では、視力への影響が少ない場合に限り、まずは点眼薬による治療が行われます。よく使われる薬には、ピレノキシン製剤やグルタチオン製剤などがあり、水晶体のたんぱく質が変性・濁るのを抑える作用があります。これらの点眼薬は、白内障の進行をゆるやかにする目的で使用されるものです。
ただし、点眼薬では水晶体の濁り自体を改善したり、透明な状態に戻したりすることはできません。そのため、点眼治療だけで視力を回復させることは難しく、濁りが進んで見えづらくなってきた場合には、手術を検討する必要があります。
日常生活への影響が少ないうちは、定期的な眼科検診を受けながら、進行の度合いを見守ることが大切です。
また、紫外線を避けるためにサングラスを活用したり、室内照明の調整を行ったりすることも、進行を抑える手助けになります。点眼治療とあわせて、こうした生活上の工夫を取り入れることで、より長く視力を維持することが可能になります。
進行している場合
白内障が進行し、視力が落ちて日常生活に支障を感じるようになると、手術による治療が必要となります。
白内障は進行が緩やかなことが多く、自覚症状に乏しいケースもありますが、運転や読書、仕事などに支障をきたすようになったら、手術のタイミングです。手術の実施時期については、医師との十分な相談のもとで決定されます。
現在、もっとも広く行われているのは、超音波乳化吸引術と呼ばれる手術方法です。この手術では、角膜を小さく切開し、超音波で濁った水晶体の中身を砕いて吸い出した後、眼内レンズを挿入します。
局所麻酔で行われ、手術時間は10〜30分程度です。ほとんどの場合、日帰りでの対応が可能です。
手術後は、視力が安定するまでに数週間から1ヶ月程かかります。その間は、感染予防や炎症を抑えるための点眼薬を継続し、通院しながら経過を観察します。
また、術後しばらくは洗顔や入浴、運動などに制限があるため、医師の指示にしたがって慎重に生活する必要があります。
白内障手術後の注意点
白内障の手術後は、目をできるだけ早く回復させるために、いくつかの注意点があります。具体的には、以下のポイントを守ることが大切です。
医師の指示を守り生活する
何よりまずは、医師の指示を守りましょう。
例えば、手術後に処方された抗菌薬や炎症を抑える点眼薬を、医師の指示どおりにきちんと使い続けることなどが挙げられます。点眼薬には感染予防や炎症軽減の役割があり、これを怠ると眼内炎などの合併症が起きるリスクが高まります。
また、定期検診を受けることも重要です。医師が目の状態を確認することで、早期に異常を発見し対応することができます 。
目をこすらない・強く押さえない
手術直後は傷口が完全にふさがっているわけではないため、目をこすったり強く押さえたりといったことは避けましょう。
たとえ無意識でも手で触れることで、細菌の侵入による感染が起こる可能性があり、眼内炎など重篤な状態につながる恐れがあります。特に就寝時にも眼帯をつけて保護するようにし、外出時は紫外線やほこり、風から目を守るサングラスなどを装着するのがおすすめです。
激しい運動は1ヶ月程度控える
手術後、軽い散歩やデスクワークは翌日から可能となることが多いですが、運動や家事でも目に圧力がかかる行為は控えた方がよいとされています。
軽く汗をかく程度なら1週間程、ランニングや筋トレなど負荷が大きい運動は2〜4週間程度、強度の高いスポーツや重い荷物を持つ行為は1ヶ月程度控える必要があります。これは、腹圧などで目のなかの圧力が上がることで傷の治癒が妨げられたり、出血が起きるリスクがあるためです。より具体的な再開時期については、医師に確認するとよいでしょう。
視界のかすみや痛み、充血が続くときはすぐ受診する
術後は目が乾いたり充血したりして違和感を覚えることがありますが、多くの場合は数日から数週間で落ち着きます。
しかし、視界のかすみが悪化する、痛みが強い、充血が続くなど普段と違う症状が現れた場合は、合併症が疑われます。このような症状がある場合は、すぐに眼科を受診するようにしましょう。
まとめ
白内障は、早い人では40代から発症し、高齢になる程誰にでも起こる可能性が高まる目の病気です。視界のかすみやまぶしさなどの症状は徐々に進行するため、年齢のせいと見過ごしてしまうことも少なくありません。日常生活で見え方に違和感を覚えたら、年齢に関わらず、早めに眼科で相談することが大切です。
目が見えなくなると聞くと怖い気持ちになるかもしれませんが、治療によって多くの患者さんが大きな問題なく日常生活を送れています。「白内障は誰でも、いつでも起こりうる」という考えのもと、備えておくことが大切です。
参考文献
