物が歪んで見える場合、もしかしたら手術が必要な眼の病気があるかもしれません。
この記事は、物が歪んで見える場合に疑われる病気の種類や、正常な状態を取り戻すために行われる治療法の種類、そして目のトラブルを予防するための方法などを解説します。
歪んで見える状態とは
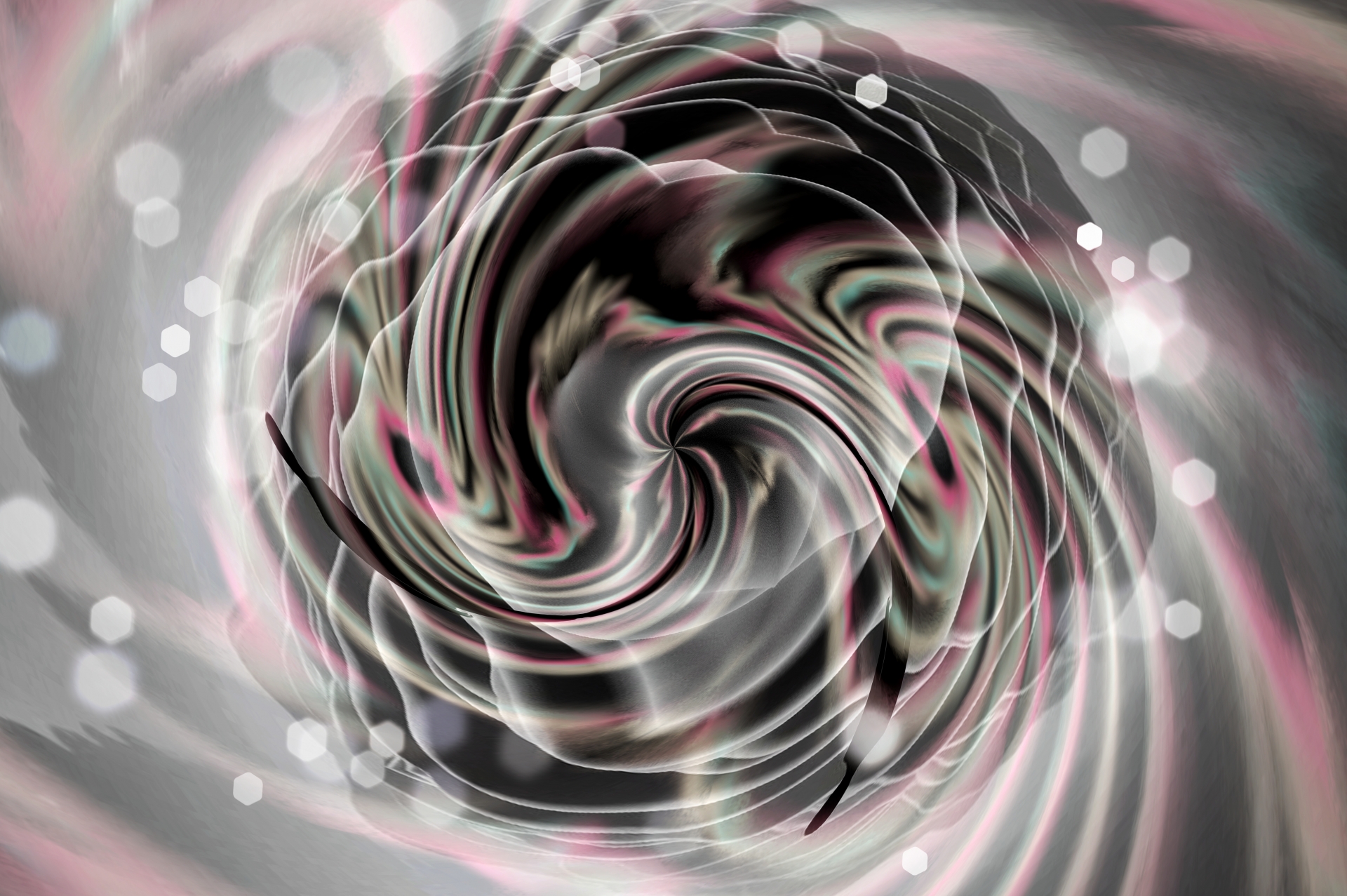
まっすぐのはずのものが曲がって見えるなど、目に何かしらの異常があると、物が歪んで見えることがあります。
まずは、なぜ歪んで見えるのかについての理由や、歪んで見える状態になっているかどうかのセルフチェック方法を紹介します。
歪んで見える歪視(わいし)とは
まっすぐの線が波打ったり、曲がってみえたりする状態を、歪視または変視症と呼びます。
物を見るという機能は、眼球内に入ってきた光が網膜に届き、その情報が視神経を通じて脳で処理されることで行われます。
歪視の多くはこの網膜の中心部にある黄斑という部位に何らかの異常が生じることで発生するもので、さまざまな目の病気が網膜の異常を引き起こす要因となります。
歪んで見えているかどうかのセルフチェック方法
歪んで見える状態になっているかどうかは、アムスラーチャートと呼ばれる、方眼紙のように縦横に規則的な直線がひかれ、中央に黒い点が描かれたチェックシートを使用してセルフチェックが可能です。
このチェックシートの中心にある黒い点を、30cmほど離れた距離から片目ずつ見て、直線に歪みがないかどうかを確認しましょう。
このチェックは歪視だけではなく、さまざまな見え方のトラブルをセルフチェック可能なので、定期的なセルフチェックとして取り入れるとよいでしょう。
歪んで見える場合に疑われる病気

物が歪んで見える場合、下記のような病気が疑われます。
黄斑前膜(網膜前膜)
黄斑前膜は、網膜の中心にある黄斑部分に、薄い膜が張り付いてしまう病気です。網膜前膜や網膜上膜、黄斑上膜などと呼ばれることもあります。
加齢に伴って自然に生じる特発性のものと、網膜剥離などの病気に伴って生じる続発性のものがあり、40歳以上の5%程度がなるといわれています。
初期の頃は特に症状がありませんが、黄斑部分に張り付いた膜が縮むと網膜にしわがより、歪んで見える原因となります。
病気の進行がゆっくりで、すぐに重大な問題につながるものではない場合が多いため、自覚症状が軽い場合は治療を行わず経過観察のみとなるケースもあります。治療する場合は膜を除去する処置が必要で、硝子体手術が行われます。
加齢黄斑変性
加齢黄斑変性は、網膜の中心部にむくみや出血が生じ、これによって視界が歪んで見える状態になったり、視力が低下したりする病気です。
病名のとおり加齢に伴って生じるもので、黄斑部網膜にある老廃物を処理する働きが老化によって衰え、蓄積された老廃物によって網膜の組織に問題が引き起こされると考えられています。
症状の進行が緩やかな萎縮型と、急速に進行する滲出型があり、日本人は滲出型が多いとされています。症状が進行して網膜の細胞が破壊されてしまうと視力を取り戻すことができなくなるため、早期発見と早期治療が重要な病気です。 なお、加齢黄斑変性は身体の機能の老化が主な原因であるため、現在の医学では病気を完治させることは困難とされていることから、加齢黄斑変性に対する治療は、加齢黄斑変性によって生じる、脈絡膜新生血管という異常血管の解消を主な目的として行います。
脈絡膜新生血管は滲出型加齢黄斑変性で生じるもので、この血管が破れて出血などが生じることが、視力低下の要因となります。そのため、硝子体注射やレーザー光凝固術で脈絡膜新生血管を解消することで、視力低下を防ぐことが可能となります。
黄斑円孔
黄斑円孔は、黄斑部に小さな穴ができてしまい、これによって視力低下や歪んで見える状態、視界が欠けた状態などが引き起こされる病気です。
黄斑円孔も加齢に伴う変化で生じるほか、外部からの強い衝撃によるものや、病的近視に伴って生じるものなどがあります。
放置しておくと視力低下が進行するため、見つかった場合は早期に硝子体手術によって治療します。
偽黄斑円孔
上述の黄斑円孔に見えるものの、実際には黄斑が凹んだ状態になっているだけで、穴が開いているわけではない状態を偽黄斑円孔と呼びます。
黄斑前膜によって生じるもので、治療には黄斑前膜を取り除く硝子体注射などが必要となりますが、実際に穴があいているわけではないので、視力に大きな問題がなければ経過観察となることもあります。
網膜が引っ張られて凹んだ状態になっているため、視界に歪んで見える場所が生じます。
黄斑浮腫
黄斑浮腫は、黄斑部に液状の成分がたまって浮腫(むくみ)を引き起こし、これによって歪んで見えるなどの症状が現れるものです。
浮腫が続くと網膜の神経にダメージがおよび、回復が困難な視力低下を引き起こす場合があります。
治療法としては、浮腫を抑制する薬剤を眼球内に注射する硝子体注射や、網膜を焼き固めて浮腫を防ぐレーザー光凝固術、そして症状などによっては硝子体手術が行われます。
網膜剥離
網膜は10層の組織によって構成されています。一番深い層が網膜色素上皮と呼ばれる層で、何らかの原因で網膜が網膜色素上皮からはがれてしまう状態を、網膜剥離と呼びます。
網膜剥離は小さなごみのようなものが見える飛蚊症や、閃光のようなものが見える光視症などが前駆症状として現れることが多く、進行すると視野の欠損や、歪んで見えるといった症状が引き起こされます。
中心性漿液性網脈絡膜症(ちゅうしんせいしょうえきせいみゃくらくもうまくしょう)
中心性漿液性網脈絡膜症は、黄斑部の近くに栄養を供給する脈絡膜と呼ばれる部分の血管から水分がにじみ出て、それが黄斑付近にたまることで網膜剥離を引き起こす病気です。
網膜剥離により歪んで見える症状が出るほか、中心暗点という視界の中心が暗く見える症状が出る場合があります。
病変部の位置に応じてレーザー治療や内服薬での治療が行われますが、自然に治癒することもあるため、経過観察となる場合もあります。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は生活習慣病である糖尿病の合併症として生じるもので、高い血糖により網膜にある細い血管がダメージを受け、変形や閉塞を引き起こすものです。
血管が閉塞すると網膜が酸欠状態に陥るため、酸素不足を補おうとして新しい血管を作り出します。しかし、この血管はとても脆く出血しやすいため、網膜にカサブタのような膜を作り、これによって網膜剥離などが引き起こされる場合があります。
レーザー光凝固術で網膜の新生血管を焼いて失明を予防する治療や、硝子体手術による治療が行われますが、同時に糖尿病の治療として血糖値をコントロールすることが大切です。
網膜硝子体牽引症候群
網膜硝子体牽引症候群は、眼球内にあるゲル状の硝子体が加齢によって液化して網膜から離れる際、網膜を引っ張ってしまい形が歪むものです。
網膜と硝子体の癒着が強い部位で生じやすいのですが、黄斑は硝子体との癒着が強い部分のため、歪みが生じやすく、硝子体黄斑牽引症候群とも呼ばれます。
網膜静脈閉塞症
網膜静脈閉塞症は、網膜の静脈が血栓により閉塞を引き起こしたものです。静脈の閉塞によって血管から水分や血液が漏れることで、網膜浮腫や黄斑浮腫が引き起こされると、視界が歪んで見える状態になります。
血栓が原因であるため、脳梗塞などと同じく高血圧からの動脈硬化によって生じやすくなります。
乱視
乱視は、眼球内でレンズの役割を果たす角膜や水晶体がきれいな球面ではなく楕円形であったり、歪みがあったりすることで、網膜に焦点が合わずに視界が乱れる状態です。
多少の乱視は誰にでもありますが、乱視の程度が強いとものが歪んで見えるように感じる場合もあります。
乱視はコンタクトレンズや眼鏡などで矯正するほか、レーシック手術やICL手術での治療が可能です。
歪んで見える場合の治療法

物が歪んで見えるような症状がある場合、手術も含めて下記のような治療法があります。
光線力学的療法
光線力学的療法は、光に反応して活性酸素を作り出すビズダインという薬剤を点滴で投与したうえで、網膜の中心部に特殊な波長のレーザーを照射するという治療法です。ビズダインは新生血管に集まる性質があり、この治療によって新生血管を閉塞させることができます。
加齢黄斑変性など、網膜に脈絡膜新生血管が生じている場合の治療として行われます。
レーザー光凝固術
レーザー光凝固術は、レーザーの光によって生じる熱によって、眼球内の特定の部位を凝固させる治療法です。レーザーの照射は0.01~0.2秒程度と一瞬なので、痛みを感じることは基本的にありません。
網膜に生じている新生血管を防ぐ治療や、網膜剥離の初期段階で小さい穴が開いた際に、その周囲を光凝固して進行を食い止める治療などとして行われます。
硝子体注射
眼球内はにある、ゲル状の液体で満たされた硝子体と呼ばれる部位に、薬剤を注射する治療が硝子体注射です。
注射する薬剤にはさまざまなものがあり、新生血管の成長を促すVEGFという物質の働きを抑える抗VEGF薬や、ステロイド剤などを症状に応じて注射します。
硝子体手術
硝子体手術は、眼球内の硝子体にや網膜に対する手術全般を指すもので、硝子体中の濁りや出血の除去、網膜前膜の除去、そして剥がれた網膜を眼球の壁にくっつけるなどの目的で行われます。
硝子体手術とは

硝子体手術とはどのような具体的にどのように行われるのかなど、解説します。
硝子体手術の目的
硝子体手術は、硝子体内の濁りや、網膜の問題を解消する目的で行われます。ただし、硝子体手術は眼科の治療のなかでも特に高度な技術と設備が必要であり、リスクや副作用もあることから、軽度の症状などに対して行われることはあまりありません。
薬物療法やレーザーによる治療、硝子体注射などほかの治療法で十分な治療効果を得ることが難しい場合の手段として行われるケースが多いといえます。
硝子体手術の方法
硝子体手術は、局所麻酔下で行われます。点眼などによる麻酔を行ったうえで眼球に小さい穴を開けて、そこから専用の器具を挿入します。1ヶ所は眼圧を保つために液体を注入するためのもので、ほかに照明器具や切除用の器具、ピンセットのような器具を差し込み、慎重に手術を行います。
手術後は必要に応じてガスなどを注入し、吸収糸による縫合か、切開範囲が小さい場合は無縫合で手術完了となります。
硝子体手術の適応
硝子体手術は、物が歪んで見える原因となる黄斑前膜や黄斑円孔、黄斑浮腫、網膜剥離、網膜硝子体牽引症候群、網膜静脈閉塞症と幅広い病気で適応となります。
そのほかにも、硝子体出血や硝子体混濁といった、硝子体内に濁りが生じる病気でも適応となる場合があります。
硝子体手術のリスクや副作用
硝子体手術は稀に眼内炎や駆逐性出血などの合併症が引き起こされ、失明などにつながるリスクがあります。
また、手術の後は充血やゴロゴロ感、痛みなどが生じ、見え方が安定するまでに半年から1年程度の期間が必要となる場合もあります。
目のトラブルを予防する方法

手術が必要となる、物が歪んで見えるような病気にならないためには、日頃からの予防が大切です。
目のトラブルを予防するため、下記のような点に注意して過ごすとよいでしょう。
紫外線を予防する
加齢黄斑変性など、加齢によって生じるトラブルは、紫外線による網膜のダメージが蓄積されることでも生じやすくなります。
サングラスなどによる紫外線対策を徹底し、目の紫外線によるダメージを予防しましょう。
栄養バランスのよい食事を心がける
網膜の細胞も、食事によって摂取した栄養の影響を受けます。偏った食事は細胞の代謝を低下させ、トラブルを引き起こしやすい状態につながりますので、バランスのよい食事を心がけましょう。
また、活性酸素による悪影響を軽減するための抗酸化ビタミンや、黄斑を保護する色素ルテイン、目を保護する効果が期待できるオメガ3脂肪が含まれた食品などは積極的にとるとよいでしょう。
生活習慣を改善する
糖尿病や高血圧、動脈硬化といった生活習慣病は、目のトラブルを引き起こす大きな要素です。十分な睡眠や適度な運動など、良好な生活習慣を心がけ、必要であれば内科での生活指導なども受けましょう。
また、喫煙習慣は加齢黄斑変性などを引き起こす大きな要因ですので、喫煙している方は禁煙に取り組みましょう。
定期的に眼科検診を受ける
眼科での定期的な検診を受けることで、何かトラブルが生じている場合でも早期発見、そして早期治療が可能になります。
多くの病気は早めに治療を開始できれば、大がかりな手術までしなくてもコントロール可能な状態を維持できますので、定期的な検診を受けるようにしましょう。
見え方に違和感があれば早めに眼科を受診する
何か見え方に違和感があれば、我慢したり放置したりせず、早めに眼科を受診することが大切です。
病気をできる限り早く見つけ、手術などに頼らない治療を行えるようにしましょう。
まとめ

物が歪んで見える状態は、さまざまな眼科疾患によって引き起こされる可能性があります。
症状の進行状況によっては手術が必要となりますが、早期発見ができれば手術以外の方法でケアできる可能性も高くなるため、定期的な眼科健診や、早期の眼科受診で病気を早く治療することが大切です。
参考文献
