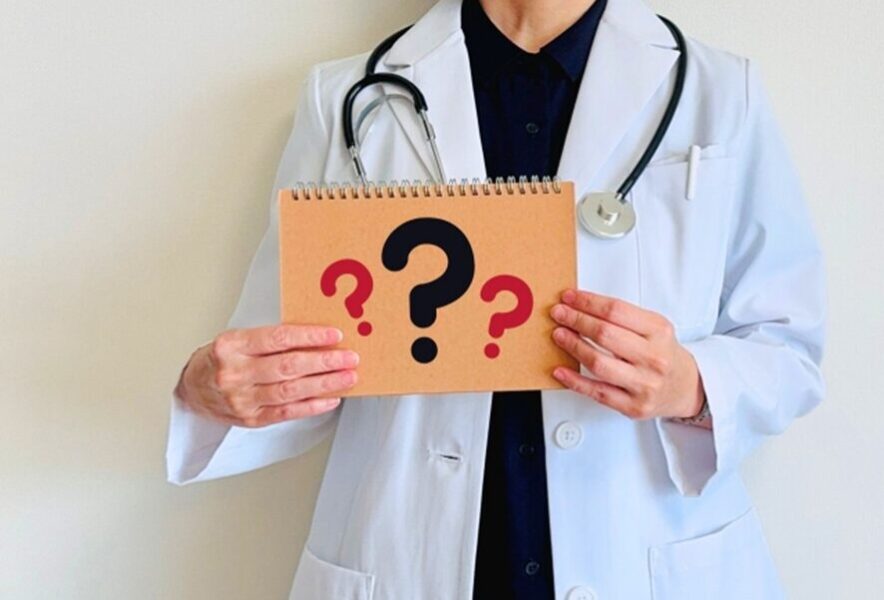最近、光がやけにまぶしい、と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。白内障は、目の中で透明なレンズの役割を果たす水晶体が濁ってしまう病気です。主な原因は加齢で、早い方では40代から濁り始め、80代になると多くの方に白内障が生じるといわれています。水晶体が白く濁ると、視界がかすんだりぼやけたりしますが、それだけでなく、光をまぶしく感じることがあります。本記事では、白内障で光がまぶしいと感じる理由や、白内障の進行に伴う見え方の変化、手術などを詳しく解説します。
白内障は光がまぶしいと感じる?

白内障ではかすんで見える、などの症状を思い浮かべる方が多いかもしれません。実は、白内障になると、光をまぶしく感じる羞明(しゅうめい)といわれる症状が現れることがあります。羞明は白内障の患者さんの代表的な症状の一つです。明るい屋外で太陽の光をまぶしく感じたり、車のライトがとてもまぶしく感じられたりします。最近やけにまぶしく感じる場合には白内障が原因の可能性があります。
白内障で光がまぶしいと感じる理由

白内障は、目のレンズの役割を果たす水晶体が濁ることで、視力低下などを引き起こす病気です。白内障で光がまぶしいと感じる理由を、水晶体の役割も含めて解説します。
水晶体の役割
目に入った光は角膜、水晶体(すいしょうたい)、硝子体(しょうしたい)と呼ばれる部分を順に通過して、目の奥にある網膜に到達します。このうち、角膜と水晶体はレンズ、網膜はフィルムに相当します。水晶体は透明で柔軟性に富んでおり、水晶体の厚みを変えて、カメラのレンズのようにピントを調節しています。このように、健康な水晶体は透明で、光をしっかり屈折させて網膜に像を結ばせます。
白内障でまぶしいと感じる理由
白内障は、水晶体を構成する蛋白質が変性し、濁りが生じる病気です。さまざまな原因で、もともと透明だった水晶体に濁りが生じると、目がかすんだり、色の見え方が変わったり多くの症状が現れます。では、なぜ白内障になると光がまぶしく感じるのでしょうか。
まぶしく感じる理由は、濁った水晶体が光を乱反射、散乱させるためです。正常な無色透明の水晶体の場合、光は目の中を直線的に通過していきます。白内障では濁っている部分で光が乱反射、散乱され、これによりまぶしさを感じると考えられています。
白内障による見え方の変化

白内障は、初期にはあまり症状がみられないことが多いとされています。白内障の症状は、病気の進行とともに徐々に現れます。ここでは、白内障の初期・中期・後期の見え方の違いを、順に見ていきましょう。
白内障の初期の見え方
白内障の初期では、自覚症状がほとんどありません。水晶体の濁りがわずかであり、軽い目のかすみや目の疲れなどの症状のみであり、多くの方が異変に気付きにくいとされています。そのほかには、明るい屋外での軽くまぶしさを感じたり、夕方の運転時に見にくい感じがしたりするなどのごく小さな変化がみられることもあります。視力への影響はなく、日常生活に支障をきたすこともありません。加齢とともに水晶体の変化が始まりますが、白内障を初期の段階で自覚するのは難しいことが多いとされています。
白内障の中期の見え方
白内障の中期になると、白内障の濁りが進み、少しずつ症状が現れてきます。視界がかすんで全体に霞がかったようになったり、明るい屋外や照明の下でやけにまぶしいと感じるようになったりします。夜間の視力低下を自覚したり、運転時に対向車のライトがとてもまぶしく感じたりします。
このように中期には症状が出始め、日常生活に影響を与えることも増えてきます。自覚症状が出てくるため、この段階で白内障と診断される方が少なくありません。一方、この時期でも自覚症状を感じにくい方もいます。
白内障の後期の見え方
白内障の後期になると、水晶体全体が白く濁ってくるため、症状ははっきりとみられます。時には重度の視力低下をきたすことがあります。水晶体全体が濁る状態は、成熟白内障と呼ばれ、この頃になると水晶体は外から見ても白く濁って見える場合があります。視界は常に霧がかかったようにぼやけ、明るい場所で強いまぶしさを感じることがあります。日常生活にも大きな支障が出ます。
過熟白内障
さらに白内障が進行すると、過熟白内障と呼ばれる状態になります。水晶体は白く濁っている状態を通り越して茶色に変色し、とても硬くなります。過熟白内障では光をまったく感じなくなる失明のリスクも高くなるといわれています。このように、白内障は放置すると大変深刻な視力障害につながるため、症状に気付いたら早めの対応が重要です。
白内障の治療方法

白内障の治療法は、点眼薬による治療と手術の二つが挙げられます。ここではそれぞれの治療法を解説します。
点眼治療
白内障の初期には、点眼薬(目薬)での治療が行われることがあります。ただし、点眼薬は水晶体の濁りをとって白内障を改善させるものではなく、あくまで進行を遅らせる目的で使用されます。このため、基本的には日常生活に支障のない、初期の白内障に対して選択されます。点眼薬を継続しながら定期的な眼科受診を続け、必要と判断された時点で手術に踏み切ることになります。
手術
白内障手術は現在、白内障に対する効果的な治療法とされています。手術を行うかどうかは、それぞれの患者さんの状態に合わせて、医師と相談したうえで決定されます。白内障手術は、以前は目の膜を大きく切開していましたが、現在は小さな切開で手術ができるようになっています。手術の方法は、超音波で水晶体を砕いて吸い出し、目の中に人工のレンズ(眼内レンズ)を挿入する方法が主流です。
麻酔は点眼での麻酔や局所の麻酔が行われ、痛みもほとんどないといわれています。患者さんの身体への負担も大きくはない手術で、日帰り手術も可能です。
白内障手術後の見え方

白内障の手術の後は、濁った水晶体が取り除かれ、透明なレンズが入ることで、光が十分に目の奥まで届くようになります。このため、今まで霧がかっていたような視界が、とてもはっきりと見えるようになります。また、眼内レンズのおかげで視力自体も良くなります。
ただし、手術の後は、良く見えるようになるだけではなく次のような変化がみられることもあります。
- 手術の前よりまぶしく感じる
- 青みがかって見える
- 目の前に小さな黒い影が飛んでいるように見える、見えていたのが増える
これらはもともと濁った水晶体で見ていたのが、透明な眼内レンズに変わったことで出てくる症状です。時間の経過とともに落ち着いてくる症状とされていますが、悪化したり続く場合は主治医に相談するようにしましょう。
また、手術後の見え方は挿入する眼内レンズの種類によっても異なります。現在一般的に使われる眼内レンズには、大きく単焦点レンズと多焦点レンズの2種類のレンズがあります。それぞれの特徴と見え方、さらに夜間の見え方の違いを説明します。
単焦点眼内レンズの見え方
単焦点眼内レンズは、焦点距離(ピントを合わせる距離)が1カ所だけの人工レンズです。ピントが合うところははっきりと見えます。
手術前に医師と相談して、ピントを遠くに合わせるレンズか近くに合わせるレンズかを選択します。遠くにピントを合わせた単焦点レンズを入れた場合、遠くの景色や看板などははっきり見えます。しかし、手元の本やスマートフォン画面はピントが合わずぼやけるため、老眼鏡が必要になる可能性があります。一方、近くにピントを合わせたレンズを入れた場合、小さな文字は読めますが、遠くを見るのに眼鏡が必要となることがあります。
単焦点レンズは焦点が一つである分、見え方が自然でコントラスト(鮮明さ)が高い利点があります。また公的な医療保険が適用される標準治療のレンズです。
多焦点眼内レンズの見え方
多焦点眼内レンズは、焦点距離遠(ピントを合わせる距離)が遠くと近くの複数ある人工レンズです。遠くと近く(あるいは中間距離)の両方にピントが合う設計になっています。手術の後は、眼鏡を使用しなくても遠くから近くの手元まで見ることができます。そのため、読書やパソコン作業、車の運転まで、眼鏡をほとんど使わずに生活できるようになる方が多いとされています。
ただし、多焦点レンズはピントを分配する構造上、単焦点レンズに比べるとコントラスト(鮮明さ)がやや低下します。また、多焦点レンズは、暗いところで光がにじんで見えたり、光をまぶしく感じたりする症状が出やすいのも特徴です。多焦点レンズに関して、以前は完全に自由診療であり、手術およびレンズの費用は自費でした。現在は、一部が選定療養の扱いに変わり、手術費用部分は公的な医療保険が適用される場合があります。
夜間の見え方
白内障手術の後、特に夜間の見え方で注意すべきなのが、次の二つです。
- ハロー(光の周りに輪が見える)
- グレア(光がにじんで見える)
暗い所で車のヘッドライトや街灯などの強い光を見ると、光の周りに輪がかかって見える現象をハローと言います。また、光がにじんだり放射状に広がって見える現象をグレアといいます。どちらも光を眩しく感じてしまう見え方の異常で、多焦点眼内レンズを入れた方に起こりやすい現象です。ハローやグレアは多焦点レンズの大きなデメリットとも言われますが、レンズの種類によって多少の差があり、最近ではハロー、グレアを抑える設計のレンズも登場しています。
単焦点レンズの場合も暗い所で軽度のハロー、グレアが出ることはありますが、多焦点レンズほど頻度は高くありません。このような夜間の見え方への影響などさまざまな点を考えて、眼内レンズの種類を選ぶ必要があります。
白内障になりやすい人の特徴

白内障は基本的に年齢を重ねれば誰にでも起こりうる病気ですが、加齢以外にも発症を早めたり、リスクを高めたりする要因があります。加齢も含めた、白内障になりやすい方の特徴を具体的に説明します。
年齢が40歳以上
白内障は、水晶体を構成する蛋白質が変性し、濁りが生じる病気です。水晶体が濁る原因の一つであり、最も代表的なものが加齢です。40歳を過ぎた頃から、誰にでも水晶体の変化が起こり始めます。加齢によって起こる白内障を加齢性白内障もしくは老人性白内障と呼びます。
40歳を過ぎた頃から誰でも水晶体が少しずつ濁り始め、80代では多くの方が白内障を発症するといわれています。年齢が高くなるほど白内障になる可能性は高くなるため、症状が見られれば早めに眼科を受診することが大切です。
糖尿病やアトピー性皮膚炎がある
別の病気があることで、白内障を発症しやすくなることがあります。代表的なものに糖尿病とアトピー性皮膚炎があります。ここではそれぞれについて解説します。
糖尿病
糖尿病のある方は、そうでない方に比べて白内障を発症しやすいことが知られています。血糖値が高い状態が続くと、水晶体の濁りにつながり、白内障が生じやくなるといわれています。糖尿病の患者さんでは、水晶体が濁るスピードが速く、通常よりも若い年齢で白内障を発症します。30~40歳代で手術が必要になるケースもあります。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎の方も白内障になりやすいといわれています。かゆみに伴う目のこすり過ぎなどの物理的な刺激や、ステロイドといわれる薬の影響が考えられています。重度のアトピー性皮膚炎の患者さんは、若くして白内障になることがあります。
このように、糖尿病やアトピーなど全身の持病がある方は、若くても白内障に注意が必要です。
目の病気や怪我の経験がある
目のほかの病気や怪我も、白内障になりやすい原因といわれています。例えば、白内障の原因となりうる目のほかの病気は、目の中に炎症が起こるぶどう膜炎があります。ぶどう膜炎に繰り返しかかった方は、水晶体がダメージを受けてしまいます。また、治療でステロイドが使用されることもあるため、白内障が発生しやすくなります。
また、眼の怪我も白内障の原因となることがあります。目への強い衝撃で水晶体が傷つくことでおこり、短期間で急速に濁ってしまうことがあります。これを外傷性白内障といい、怪我の程度によっては、ほかの白内障と比較して急速に深刻な状態に陥ることがあります。外傷が起こってからすぐに発症したり、目の外傷後、数年経ってから白内障が出てくるケースもあります。さらに、以前に目の手術(緑内障の手術など)を受けた方も、手術の影響で白内障が進みやすいことが知られています。以上のように、目の病気や怪我の経験がある方は、定期的に眼科を受診し、白内障の兆候がないかチェックすることが望ましいでしょう。
まとめ

白内障は、年齢とともに誰にでも起こりうる病気です。進行すると視力低下やまぶしさなど、日常生活に大きな影響を及ぼすようになります。初期には気付きにくく、老眼や疲れ目と間違われることも少なくありません。特に、まぶしさは白内障の主な症状の一つです。白内障が進行すると、基本的には治療は手術が必要とされています。光がまぶしい、視界がかすむなどの症状を感じたら、早めに眼科を受診するようにしましょう。
参考文献
- 安藤 伸朗, (2016.2.17), 症状別病気解説, 白内障, 恩賜財団済生会
- 日本眼科学会, 眼の病気 眼の構造
- 日本眼科学会, 眼の病気 白内障
- Kierstan Boyd, (2024.10.9), What Are Cataracts?, American Academy of Ophthalmology
- Cleveland Clinic, (2023.7.3), DISEASES&CONDITIONS, Cataracts (Age-Related)
- 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト 先天性風疹症候群
- 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 先天白内障
- 髙橋 直巳, (2023.02.27), 白内障治療の最新事情と眼内レンズの選び方, 恩賜財団済生会
- 大鹿 哲郎(2020.12.7), 白内障手術と眼内レンズ 眼内レンズを上手に選ぶために, 日本眼科医会
- 日本白内障学会, 白内障になったらどうすればよいのか
- 市立貝塚病院 「白内障」について