白内障は、眼のなかの水晶体が濁ることによって徐々に見えづらくなる病気です。加齢とともに罹患率が上がり、80歳以上の高齢者はほとんどが発症しているともいわれています。手術をすればほぼ治すことができる病気ですが、自覚症状が出にくいため、気付かずに症状が進行してしまう場合も少なくありません。この記事では、白内障を予防するために今日からできる対策をご紹介します。また、白内障の原因や種類、症状なども詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
白内障の原因
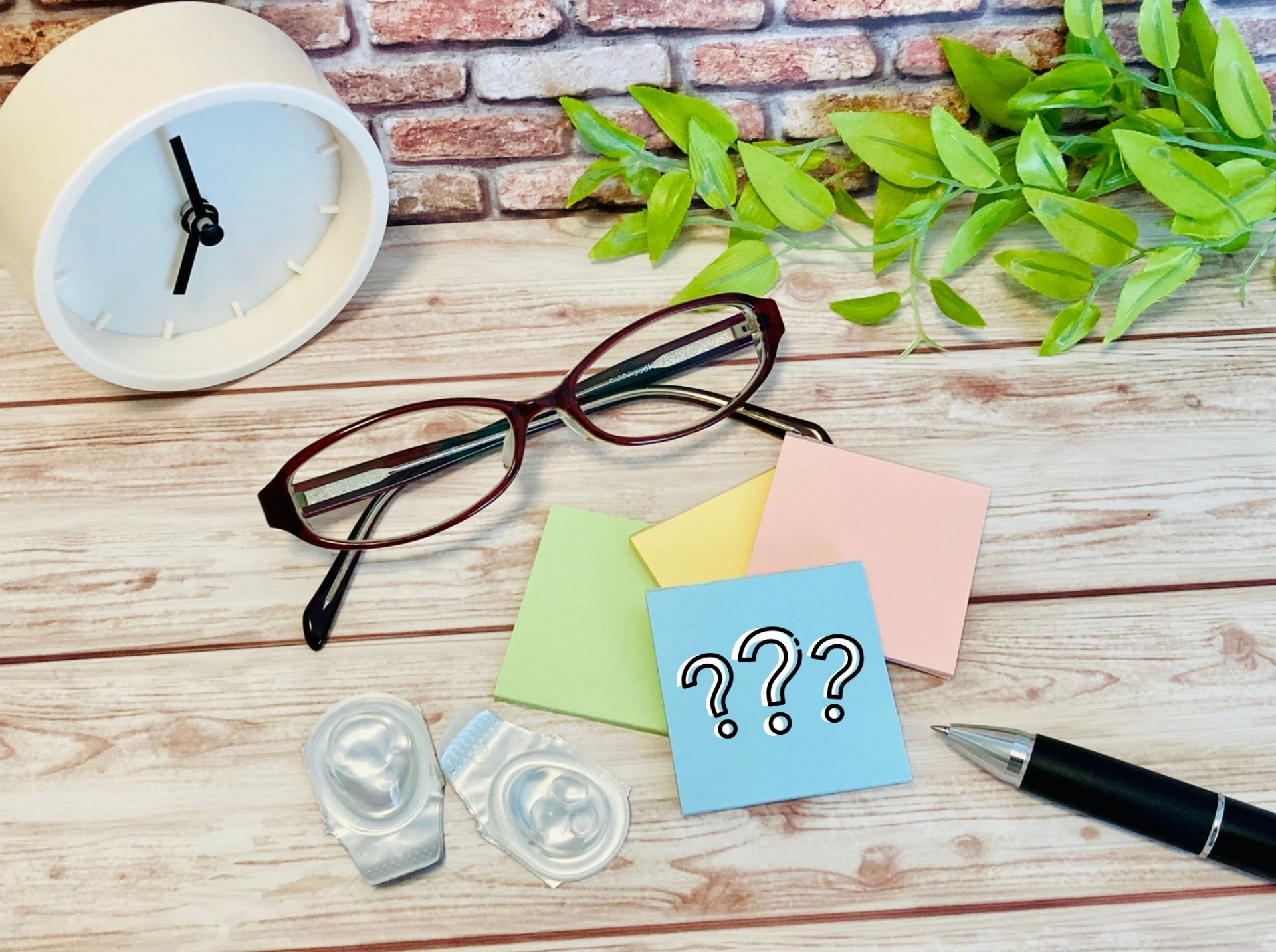 白内障は、主に加齢によって引き起こされることの多い病気です。また、生活習慣や糖尿病などの全身疾患、薬剤や外傷などが原因となることもあります。ほかにも、生まれたときから白内障を発症している先天性白内障の場合には、母胎内感染や遺伝的疾患などの可能性が考えられます。
白内障は、主に加齢によって引き起こされることの多い病気です。また、生活習慣や糖尿病などの全身疾患、薬剤や外傷などが原因となることもあります。ほかにも、生まれたときから白内障を発症している先天性白内障の場合には、母胎内感染や遺伝的疾患などの可能性が考えられます。
加齢による水晶体の変性
白内障は、水晶体の加齢による変性によって引き起こされます。水晶体は、人間の眼のなかでレンズの役割を果たしています。この水晶体の細胞内に含まれるたんぱく質が加齢によって酸化し、徐々に白く濁ってくることで白内障が引き起こされるのです。
加齢が原因となって発症する白内障は、老人性白内障または加齢性白内障とも呼ばれ、50歳を超えた頃から発症の確率が上がります。早い方の場合は40代から発症し、80歳ではほぼ100%の方に白内障の症状が見られるようになります。ただし、高齢の方の場合は自覚症状が出にくいこともあります。このため、ご家族の方から眼科の受診をすすめるなどの対応をとることをおすすめします。高齢の方に限らず、40歳以上の方で見え方に異常を感じる場合は、早めに眼科の検診を受けるようにしましょう。
生活習慣の影響
水晶体の細胞の酸化は、加齢以外の外因によっても起こります。特に影響が大きいとされるのが、紫外線などの環境ストレスや飲酒、喫煙といった生活習慣です。日焼けの原因にもなる紫外線は、水晶体のたんぱく質の酸化を加速させます。イメージとしては、卵の白身が熱で固まるような状態です。長時間紫外線を浴び続けることは、なるべく避けるようにしましょう。
アルコール摂取も白内障のリスクを高めるとされています。特に男性の場合、毎日飲酒をする方は、飲酒が月一回未満の方に比べて白内障の相対危険度が高まるだけでなく、大量のアルコール摂取が核白内障を増加させることにもつながります。また、喫煙についても、白内障のリスクとなることがわかっています。たばこから発生する窒素酸化物は、水晶体内のたんぱく質に悪影響があるとされています。さらに、たばこに含まれるニコチンは毛細血管を収縮させるため、血液障害が起こることで白内障のリスクが高まります。飲酒や喫煙はほかの疾患のリスクともなりますので、控えることをおすすめします。
糖尿病などの全身疾患
糖尿病などの全身疾患によって白内障を発症する場合もあります。糖尿病は、インスリンの分泌異常により血糖コントロールができず、ソルビトールという物質が蓄積します。ソルビトールとは糖の一種であり、白内障の発症リスクを高めると考えられています。糖尿病がある場合の加齢性白内障は進行が早いとされているため、糖尿病の患者さんは自覚症状の有無を問わず眼科での定期的な検査を受けることをおすすめします。糖尿病を患っている方は糖尿病網膜症という合併症を発症することもありますので、こうした病気の早期発見をする意味でも、定期検査を欠かさないようにしましょう。
ステロイド剤の長期使用や目の外傷
アトピー性皮膚炎などの治療の際に使用されるステロイド剤は、長期間使用すると白内障のリスクを高めるといわれています。また、アトピー性皮膚炎のかゆみなどによって目を掻いたり、叩いたりすると、その刺激によって白内障を発症することもあります。このほかにも、物が目に当たったり、事故にあったりして目に衝撃を受けると、外傷性白内障を引き起こす可能性があります。外傷性白内障は、ほかの白内障と比べて急速に水晶体が白濁するケースもあることから、早急な手術が必要となる場合も少なくありません。目に衝撃を受けた際は、すぐに眼科を受診するようにしましょう。さらに、衝撃を受けた数年後に発症することもあるため、その後も定期的な検診を欠かさないようにすることが大切です。
白内障の種類
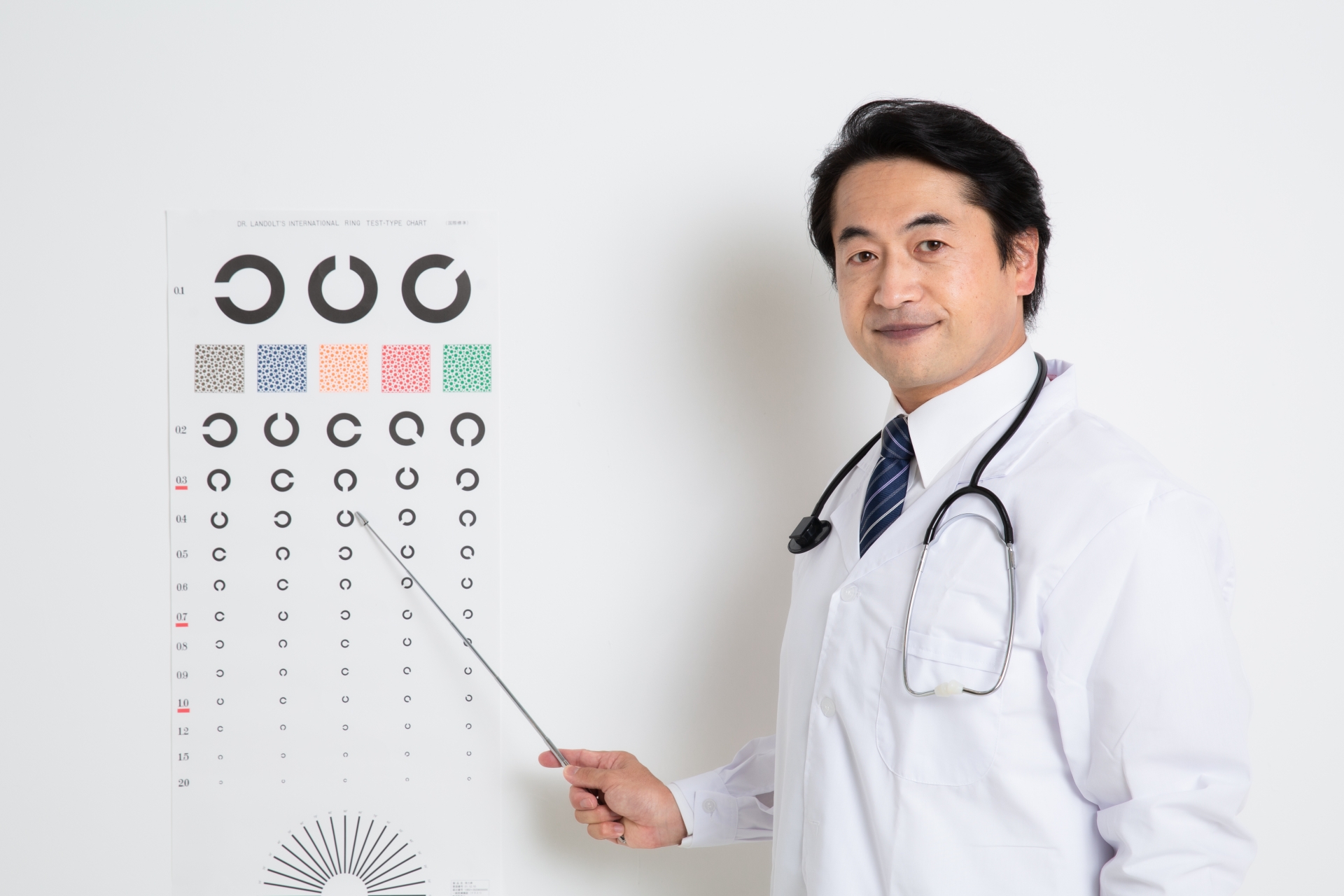 白内障は、その原因によっていくつかの種類に分けられます。ここでは、老人性白内障、糖尿病性白内障、先天性白内障、外傷性白内障の4つを詳しく解説します。
白内障は、その原因によっていくつかの種類に分けられます。ここでは、老人性白内障、糖尿病性白内障、先天性白内障、外傷性白内障の4つを詳しく解説します。
老人性白内障
老人性白内障は、別名を加齢性白内障ともいい、加齢によって引き起こされる白内障のことを指します。このタイプの白内障は、全体の90%を占めるとされており、一般的な白内障とされています。年齢が上がるにつれて罹患率も高くなりますが、早い場合は40代で発症するケースもあります。老人性という名前に惑わされず、40歳を過ぎて目に違和感を覚える場合は、早めに眼科を受診するようにしましょう。老人性白内障は、80歳以上の高齢者は発症している可能性が極めて高いとされていますが、一方で高齢者の場合、自覚症状が出にくいという特徴もあります。家族に80歳以上の方がいる場合は、一度受診を促すなどの対応をとるようにしましょう。
糖尿病性白内障
糖尿病の合併症として引き起こされる白内障を、糖尿病性白内障といいます。糖尿病は血糖値のコントロールが不安定になる病気で、ソルビトールと呼ばれる糖の一種が水晶体のなかに蓄積することで白内障を引き起こすリスクが高くなります。また、糖尿病の患者さんは、糖尿病網膜症という別の目の病気を発症するリスクも高いため、目に異常がなくても、定期的に眼科を受診してこれらの病気の早期発見に努めてください。
先天性白内障
先天性白内障とは、生まれたときから白内障を発症しているケースを指します。発症の要因はさまざまあり、遺伝的な問題から発症する場合や、全身疾患による場合のほかに、妊娠中に風疹などの感染症に罹患した母親から生まれた子どもが発症する場合もあります。先天性白内障では、外からの光が網膜に届きにくくなることで新生児の視力の発達が遅れる可能性も高いため、できる限り早期に手術をする必要があります。目の揺れが起こる眼振や、片眼の視線がずれる斜視などの弱視の症状がある場合は、放置をすると治療困難となるケースも少なくありません。よい視力を獲得するためには、両眼性の場合は生後10週、片眼性の場合は生後6週までに手術を受ける必要があります。
外傷性白内障
外傷性白内障は、物が目に当たったり、怪我をしたりなど、目に衝撃を受けた場合に発症します。ほかの白内障が徐々に進行するのと比べて、外傷性白内障の場合は症状が急激に深刻な状態へとなることも少なくありません。目に衝撃を受けた場合は、ただちに眼科を受診するようにしましょう。また、外傷を負った直後ではなく数年後に白内障を発症することもあるため、その後も定期的に眼科検診を受けることをおすすめします。
白内障の主な症状
 白内障は初期にははっきりとした自覚症状が現れることが少ないといわれています。これは、一方の眼の異常をもう片方の眼がカバーすることにより、ある程度までは日常生活に支障を感じないことが原因です。しかし、進行すると徐々に見づらい状態となります。ここでは、白内障の症状として挙げられる特徴について解説します。
白内障は初期にははっきりとした自覚症状が現れることが少ないといわれています。これは、一方の眼の異常をもう片方の眼がカバーすることにより、ある程度までは日常生活に支障を感じないことが原因です。しかし、進行すると徐々に見づらい状態となります。ここでは、白内障の症状として挙げられる特徴について解説します。
視界がかすむ・白っぽく濁る
白内障の一般的な自覚症状として、視界がかすんだり、白っぽく濁ったりするという現象が挙げられます。これは、本来透明であるはずの水晶体が白濁し、光の透過性が落ちるために起こります。くもりガラスを通して見ているように、なんとなく物がかすんで見えたり、ピントが合いにくいといった症状があれば、白内障のサインの可能性があります。
まぶしさや光のにじみを感じる
白内障を発症すると水晶体が濁って光が真っ直ぐに網膜に届かず、光が散乱するように見えることがあります。このため、まぶしさや光のにじみを感じるという症状が出やすくなります。特に、夜道で明るい街灯や信号を見たときなどにこのような現象が起きる場合が少なくありません。また、夜間の車のヘッドライトなどもまぶしく感じるようになります。このような場合は、車の運転を控え、早めに眼科を受診するようにしましょう。
物が二重に見えることがある
物が二重に見える、という症状も白内障の自覚症状のひとつです。ただし、物が二重になって見える場合が常に白内障によるものとは限りません。眼鏡をした状態で片眼ずつ月を見たときに二重や三重に見える場合は、乱視や白内障の可能性があります。また、両方の眼で見たときは二重や三重に見えるのに片眼を閉じたら消える場合は、脳神経の病気の可能性もあります。
視力低下
視力の低下も、白内障の症状のひとつとして挙げられます。しかし、白内障を発症したすべての人が初期から視力低下を実感するわけではありません。むしろ、白内障の症状が進行してから現れることの多い症状といえます。これは、水晶体の濁りは外側から中心部に向かって徐々に進行することが多く、中心部が濁るまでは視力の低下を実感しづらいためです。早期から中央部に濁りが生じるタイプの白内障でなければ、自覚することが難しいため、視力低下がないからといって、白内障を発症していないということにはなりません。
今日からできる白内障対策
 では、白内障を予防するにはどのような対策が効果的でしょうか? ここからは、今日からできる白内障対策を5つご紹介します。
では、白内障を予防するにはどのような対策が効果的でしょうか? ここからは、今日からできる白内障対策を5つご紹介します。
紫外線対策
白内障の原因である水晶体の濁りは、主に紫外線による酸化によって起こります。そのため、白内障を予防するには、紫外線対策が非常に重要です。しかし、水晶体には光を集める働きがあり、紫外線による酸化の影響を完全に避けることはできません。このような理由により、誰でも加齢とともにある程度の水晶体の白濁化が進行することになるのです。白内障の発症を予防するには、目に入る紫外線量を極力減らす必要があります。紫外線カット機能のあるサングラスや、つばの広い帽子を着用するなど、しっかりと紫外線対策を取るようにしましょう。
食生活の改善
水晶体のたんぱく質は酸化により白く濁ります。この酸化を防ぐために効果があるとされているのが、抗酸化作用のある食べ物です。ビタミンCやベータカロチン、ルテイン、ゼアキサンチンなどの抗酸化物質を含んだ食べ物を摂取することで、白内障の予防が期待できます。いちごやレモン、柿などの果物、にんじん、ほうれん草、ピーマン、かぼちゃなどの緑黄色野菜、とうもろこしや焼き海苔などの食材に抗酸化作用のある物質が豊富に含まれているため、積極的に食生活に取り入れるようにしましょう。このほかにも、緑茶(せん茶)やオレンジジュースといった飲み物にも抗酸化作用があるといわれています。
適度な運動
糖尿病は白内障の発症原因となる可能性が高く、その他の眼の病気や合併症に発展する恐れもあります。そのため、糖尿病を予防することは、白内障対策にもつながります。糖尿病を防ぐためには、暴飲暴食を避け、バランスのよい食事を摂ることと、適度な運動をすることが挙げられます。健康を維持するうえでも、規則正しい生活と適度な運動は欠かせません。普段身体を動かすことの少ない方は、運動習慣を生活のなかに取り入れてみましょう。
禁酒・禁煙
前述したように、毎日の飲酒やアルコールの大量摂取は白内障のリスクを高めます。なるべくアルコールの摂取は控えるようにしましょう。また、喫煙も白内障やその他の病気を予防するうえで、とても重要です。たばこには抗酸化作用のあるビタミンCを破壊する成分も含まれているため、たばこを1本吸うごとに25〜70mgものビタミンCが減少するともいわれています。食生活を改善しても喫煙することで水晶体の酸化を促進することになってしまうため、喫煙習慣のある方は禁煙することをおすすめします。
定期的な眼科の受診
白内障は高齢になるにつれて誰もが発症する病気といわれています。しかし、初期にはほとんど自覚症状がないため、自分で気付くことは困難です。そのため、ある程度の年齢に達したら、定期的な眼科検診を受ける必要があります。検診を受けることで早期発見につながるだけでなく、水晶体の白濁が確認された場合は、進行の抑制効果が期待される目薬を処方してもらうこともできます。ただし、点眼薬の進行抑制効果については限定的であるとする意見もあるため、点眼を希望する場合は医師に相談するようにしましょう。
まとめ
白内障は、加齢や紫外線などの影響により、誰もが発症する可能性のある病気です。生活習慣を見直したり、紫外線対策を行ったりして、日常生活のなかで予防することが大切です。また、自覚症状に乏しいため、定期的な眼科検診も重要です。目に違和感があったり、見え方に異常があったりする場合は、できる限り早めに眼科医の診察を受けることをおすすめします。白内障の原因や症状を知ることで、健やかな瞳を守りましょう。
参考文献
