緑内障というと高齢者の病気というイメージがありますが、実は子どもにも起こりうる病気です。緑内障は日本人の失明原因の第1位にも挙げられる深刻な疾患であり、子どもの場合も早期に適切な対応をしなければ重い視機能障害を残すおそれがあります。そこで、本記事では子どもの緑内障について、初期症状や原因、そして治療法やその後の生活への影響について解説します。
子どもの緑内障とは

子どもの緑内障とは、小児期に発症した緑内障のことです。以前は先天緑内障や発達緑内障などと呼ばれていましたが、2017年の日本の診療ガイドライン改訂以降、小児緑内障という用語に統一されました。緑内障とは眼球内の圧力(眼圧)の上昇などにより視神経が障害され、視野の一部が欠けたり狭くなっていく病気です。
子どもの緑内障の多くは、生まれつき眼の中の液体(房水)がうまく排出されないことによって眼圧が慢性的に高くなることが原因です。房水は通常、眼の前方にある隅角から線維柱帯やシュレム管を通じて排出されますが、この隅角の発育異常があると房水の流れが滞り眼圧が上昇します。このように小児期に発症する緑内障は、原因や経過が大人の緑内障と異なる点が多く、早期発見・治療が将来の視力に大きく影響します。
子どもの緑内障の初期症状

乳幼児における緑内障の初期症状には特徴的なものがあります。代表的なのは黒目(角膜)の大径化で、黒目が通常より大きく見える場合があります。これは高い眼圧によって角膜が伸展し、眼球全体が大きくなってしまうためです。加えて、涙が出る(流涙)、光をまぶしがる(羞明)、黒目が白く濁る(角膜混濁)といった症状も見られることがあります。生後まもない赤ちゃんでは機嫌が悪く泣き止まない原因が実は緑内障だったというケースもあり、周囲の大人がこれらのサインに気付くことが大切です。特に、片方の目だけに緑内障が起きている場合、黒目の大きさの左右差から異変に気付きやすいです。
一方、幼児期後半から学童期以降に発症する緑内障の場合、眼球の拡大や角膜の濁りといったわかりやすい症状は現れにくくなります。この年代になると眼球組織がある程度硬くなり眼圧上昇に耐えてしまうため、黒目の拡大などが起こらないのです。その結果、自覚症状に乏しく病状がかなり進行するまで周囲も本人も気付かず、就学時の視力検査などで片眼の視力低下によってようやく発見されることもあります。このように発見が遅れる傾向があるため、幼児後期以降の緑内障では診断時にはすでに視野障害や弱視を生じてしまっていることも少なくありません。
子どもの緑内障の原因と検査方法
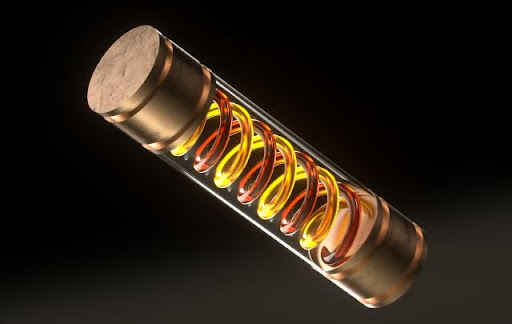
子どもの緑内障は症状の違いだけでなく、原因や検査方法などが大人と異なる点も少なくありません。そこで、本章では子どもの緑内障の原因と検査方法について解説します。
子どもの緑内障の原因
子どもの緑内障は、大きく原発小児緑内障と続発小児緑内障に分類されます。
原発小児緑内障とは、眼の房水の排出路である隅角の発育以外に明らかな原因がないタイプで、生まれつき隅角の形成不全があり乳幼児期に発症します。一方、続発小児緑内障はほかの病気や異常に伴って生じるタイプで、代表的なものに先天眼形成異常や先天全身疾患に関連した緑内障があります。例えば、虹彩が生まれつきほとんど形成されない無虹彩症、角膜と虹彩が癒着するPeters異常、あるいはAxenfeld-Rieger症候群などでは高頻度に緑内障を合併します。全身疾患ではスタージ・ウェーバー症候群や神経線維腫症、ダウン症などで合併する例が知られています。
このような続発小児緑内障では原因疾患に応じて遺伝性が認められることもあります。一方、原発小児緑内障の場合、親から子への遺伝は少なく、多くは偶然に起こります。近年の研究では、原発先天緑内障の一部にCYP1B1という遺伝子の変異が見つかることが報告されています。CYP1B1遺伝子は眼の発達や房水排出に関与する遺伝子で、この変異により線維柱帯の形成や機能に支障をきたし眼圧上昇を招くと考えられます。もっとも、この遺伝子変異が見られることは多くなく、多くの先天緑内障は原因遺伝子が特定できていないのが現状です。
その他、ステロイド薬の長期使用も小児の続発緑内障の原因になります。喘息やアレルギー性疾患の治療でステロイド点眼や軟膏を使用した場合、眼圧が上昇し緑内障を引き起こすことがあります。このように子どもの緑内障は、先天的な要因から後天的な要因までさまざまな原因で生じうるのです。
子どもの緑内障の検査方法
眼科で行われる主な検査は、大人の緑内障とおおむね共通していますが、小児では年齢に応じた配慮が必要です。本章では子どもに対して行われる検査方法について解説します。
視力検査
乳幼児の場合は視力を測定できない場合がありますが、現時点での視力を知ることは弱視の有無などを把握するうえで重要です。
眼圧検査
まず眼圧検査によって眼圧の高さを評価します。乳幼児ではじっとできないため全身麻酔下で眼圧を測定する場合もあります。手持ちの眼圧計を用いることもありますが、椅子に座れる場合は大人と同じような眼圧検査を行います。この眼圧値は緑内障の診断だけでなく、治療の有効性や手術方法の選択に必要なデータです。
細隙灯顕微鏡検査
次に細隙灯顕微鏡検査という顕微鏡で眼球の前方を観察する検査で、角膜の状態や前房の深さなどを確認します。細隙灯顕微鏡検査では緑内障の診断だけでなく、ほかの眼科疾患の有無を確認したり、角膜混濁の程度など観察にも必要です。
隅角鏡検査
細隙灯顕微鏡検査を行い前眼部を観察した後は、隅角鏡検査を行います。隅角鏡検査では特殊なレンズを用いて、隅角の発達異常や閉塞の有無を調べます。この隅角鏡検査で得られた所見は、ぶどう膜炎などの原因推定にも有用です。
眼底検査
必要に応じて超音波検査で眼軸長を測定し、片眼のみ異常に眼球が大きくなっていないか比較することもあります。超音波検査は痛みや放射線を伴わずに検査できるため、乳幼児であっても安心して検査を行うことができます。
視野検査
緑内障によって視野がどの程度障害されているかは、視野検査を用いて評価します。お子さんが小さい場合に評価するのは難しいですが、学童期であれば検査を行うことは可能です。
これらさまざまな検査を組み合わせることで、緑内障の有無だけでなく、緑内障の原因などについても調べることができます。
子どもの緑内障の治療法

子どもの場合も大人と同じように治療を行うことがありますが、緑内障の治療は大人と異なる点も少なくありません。そこで、本章では子どもの緑内障の治療法について、薬物治療と手術治療に分けて解説します。
薬物治療
子どもの緑内障に対する薬物治療は、年齢や緑内障の種類によって役割が異なります。乳幼児期発症の原発小児緑内障では隅角の形態異常が強いため、残念ながら点眼薬では十分な効果が得られないことが多く、薬物治療単独で眼圧を正常化させるのは難しいのが現状です。このため乳幼児の緑内障では薬物治療は一時的な眼圧コントロールや術前の補助的手段に留まり、基本的には早期に外科的治療を行う必要があります。
一方、それ以降で発症する緑内障の場合は、大人の緑内障と同様にまず点眼薬による眼圧下降治療を開始するのが一般的です。使用される点眼薬には、日本では小児への適応が認められている緑内障点眼薬が限られますが、医師の判断で必要に応じて使用されます。特にプロスタグランジン関連薬(いわゆるPG点眼)は第一選択薬として用いられています。ただし、小児では点眼薬の全身への影響にも注意が必要です。また、続発性の小児緑内障では、原因となっている疾患の治療や、誘因薬剤の中止が優先されます。そのうえで緑内障自体への対症療法として点眼治療を行うことになります。
手術治療
手術治療は、子どもの緑内障において視機能を守るために欠かせない治療法です。特に原発先天性緑内障では診断が確定し次第、原則として早期に手術が検討されます。子どもは大人の場合と違って、眼科手術は全身麻酔下で行われることがほとんどです。そして、入院で手術を行うのが一般的です。手術の第一選択は、隅角の詰まった排出路を切開して房水の流れを確保する手術です。具体的には、隅角を内側(眼内)から切開するゴニオトミーや、外側(眼外)から線維柱帯を切開するトラベクロトミーといった術式が行われます。どちらも線維柱帯に切れ目を入れて房水の通り道を作る手術で、眼圧を下げる効果があります。
角膜が濁っていて眼内から隅角が見えない場合はトラベクロトミーが選択され、角膜が透明ならゴニオトミーも可能です。また、重症例では一度の手術で十分な効果が得られない場合も多く、追加の手術が必要になることがあります。追加手術としては、眼圧をさらに下げるためのろ過手術(トラベクレクトミー)や、緑内障インプラント手術(チューブシャント挿入)などが行われることがあります。これらは主に思春期以降の若年者や、繰り返しの隅角手術が難しい症例に適用されます。
また、小児では創傷治癒力が旺盛で手術後の瘢痕化が起こりやすく、大人より手術効果が持続しにくい傾向があります。そのため長期的な管理のなかで追加治療が必要になるケースも少なくありません。手術後も定期的に眼圧や視神経の状態をチェックし、必要に応じて点眼治療や再手術を組み合わせて、一生にわたり眼圧管理していくことが重要です。
子どもの緑内障が将来に与える影響

小児期に緑内障を発症すると、放置すれば視力の発達段階で障害を受けてしまうため、将来的に重い視覚障害が残るリスクがあります。実際、先天性緑内障の患者さんでは治療を受けても弱視が残るケースが多く、ある研究では半数近くで最終的な視力が不良であったとの報告もあります。特に乳幼児期に発症した両眼性の緑内障では、視野狭窄や視力低下が幼少期から生じるため、適切に対処しないと日常生活や学習への支障が大きくなります。
幼少期に視力障害を負うことは、本人の心理的発達や社会的活動にも影響しうるため、早期からのリハビリテーションや支援が重要です。幸い、適切な治療によって眼圧コントロールが良好に保たれれば、視力の発達をある程度守ることができます。実際に原発先天緑内障でも、早期発見と治療により良好な視力を維持できた患者さんはいます。将来的な影響を最小限にとどめるには、できるだけ早期に眼圧を下げて視神経へのダメージを食い止めることが不可欠です。
そのためには乳幼児健診や学校検診で異常を見逃さないことはもちろん、保護者の方が日頃からお子さんの目の様子に注意を払い、少しでもおかしいと感じたら専門医を受診する心構えが大切です。また、一度緑内障と診断された場合は治療後も定期的な経過観察が必要です。緑内障は慢性的な疾患であり、一度治療して終わりではなく、一生涯にわたって眼圧管理と視野および視力確認を続ける必要があります。成長に伴って眼の状態も変化しますので、思春期、成人期になっても油断せず定期健診を受け、医師の指示を守って治療を継続することが、将来の視力と生活の質を守ることにつながります。
まとめ

子どもの緑内障は頻度こそ低いものの、生涯の視機能に重大な影響を及ぼしえる病気です。乳幼児の目が大きく見える、涙目が続く、光を異常に眩しがる、このような症状に気付いたら、できるだけ早く眼科を受診してください。また、家族に緑内障の患者さんがいる場合や、何らかの先天異常を指摘されているお子さんは特に注意が必要です。最近では小児緑内障の診断および治療技術も進歩しており、早期に治療を開始すれば将来にわたって視力を維持できる可能性が高まります。
治療の柱は適切な眼圧管理ですので、医師の指導のもと点眼や手術後の定期受診を根気強く続けましょう。定期的に目の検査を受けて病気の進行を監視し、必要な治療を速やかに行うことで緑内障の進行を防ぎ、お子さんの将来の視力を守ることができるでしょう。
参考文献
